1882年3月
あの日、我々はマリオンの指示に従って儀式を開始した。マリオンの指示は、彼が持っている「妖姐の秘密」という本に書かれていることに従ったものだ。
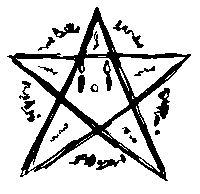 暖炉に火をおこして、床にチョークで五彗星形を描き、その中に適切な記号を描き入れた。
暖炉に火をおこして、床にチョークで五彗星形を描き、その中に適切な記号を描き入れた。
五彗星形の中央に、霊が閉じ込められている琥珀を置き、そのそばに2本の黒いローソクを立てて琥珀を照らすようにした。
みんなはそのまわりに輪になって座ったが、私は「見張り」に指名されていたから、部屋の奥の隅の床に座っていた。悪意ある霊が入ってこないように見張る役目だ。
マリオンはーつまみの粉を暖炉の中へ投げ込んだ。
すると邪悪な臭いのする煙が立ち上り、炎は小さくなって緑色と茶色にパチパチとくすぶるような感じになった。
座っていた者たちは、マリオン・アレンが本から写し取って発音できるように書きあらためたラテン語の詠唱を始めた。
約2時間近く経ったころ、私は琥珀から1すじの煙が立ち上るのを見た。
琥珀の表面は泡立っているように見え、溶けてかかってきているように見えた。
これだろうか? とうとう成功したのだろうか?
そして、私は見た。何かが・・・
![]()
その次の日だった。我々は計画をすべてやめることにしていた。
そして昨夜起こったことは2度と口にしないという約束をかわし合っていた。
ロバートの死について、それからハロルドがある種の狂気の様相を示したことについては、何とか説明をすることができた。
シェリフは馬車の事故だという我々の説明を受け入れた。我々がうまく工作したのだ。
ロバートは馬車から落ちるときに首の骨を折ったのだと我々はシェリフに言った。
またハロルドについては、馬が足を祈って馬車が転がったときに、岩で頭を打ったのだと説明した。
本当にそれだけのことだったらよかったのだが。
残りの者たちは、昨夜経験したことによって、永久的に変わってしまった。
五芒星星形の真ん中で形成された「もの」は、不定形のものでほとんど不可視のものだった。それが発した恐ろしい声によって、我々は気がついてもよかったはずなのだが、我々は愚かだった。
そいつは話した。するとマリオンがあの忌々しい粉−<イブン=グハジの粉>とか呼んでいた粉-をそいつに振りかけた。我々がそいつを見たのは、その時だった。
千もの口を持ったあいつの姿を、言葉で言い表すことはできない。
そいつはグルグルとかき混ざったり、泡立ったりするような感じで、いっときも完全な姿を見せる瞬間はなかった。
私はあまりにも驚き、恐れて、凍りついたようになって床に座っていた。
感覚のなくなった指の間からぺンが落ちた。
セシルとマリオンは私と同じように凍りついたようになっており、クロフォードは短く鋭い叫び声をあげた。
ところがロバートは立ち上がった。そして我々が止める暇もなく、恐ろしい客人を抱きしめようとするかのように、前へ進み出ていった。
怪物は手を伸ばして−と言うか、手のように見える付属器官を伸ばして、哀れなロバートをつかみ、彼の首をいとも無造作に、まるで人形の首でもひねるように簡単にグルリとひねった。
怪物はその死体を座っているハロルドのひざ上に投げてよこした。それでハロルドがあの恐ろしい金切り声を上げ始めたのだ。
彼はどうやっても金切り声を止めようとせず、我々が彼をシェリフの部下たちの手に渡した後でもずっと続けていた。
それでも我々にはまだチャンスがあった。マリオンが言うには、我々がちゃんと知性を保ち、例の詠唱を逆にして唱えることができれば、怪物をもと来た所へ返すことができるに違いないということだった。
しかしパニックに陥っていたクロフォードが五苦星形の所へ進み出ていって、図形の−部を消してしまった。そうすれば怪物を追い払うことができるとカン違いしたのだ。
束縛されていた記号から解放された生き物は、キーツという叫び声−不浄な満足の叫び以外の何物でもあるまい−を上げて家を出て行った。
沸き返る色をし、とどろき、叫ぶ一陣の風となって窓から外へ吹き去って行ったのだ。
マリオンはまだあの怪物を破壊する手段、あるいは少なくとも追い払う手段はあると信じていたが、残りの者たちはこんなことを消化できるような胃袋は持っていなかった。
しかし我々がかけた呪文は、召還した生き物を従属させる力があるから、あの怪物は家に従属させられているはずだということだった。
実際、2、3日後に自分の持ち物を取りに家に戻ってみると、上の方の屋根裏部屋でドンドンと壁や床を叩く書がしていた。
マリオンが無邪気な様子で彫り込んだあの印が効果を発揮していて、怪物は印のない屋根裏部屋を除いては家に入れなかったのだ。
マリオンが楽しげに印を刻んだあの時、我々がそれを面白がったあの時、あんな時はもう2度と返ってこない。