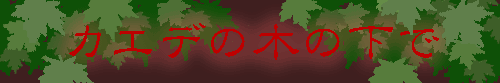|
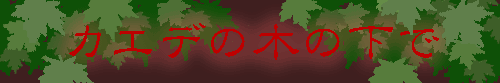
一人称のリレー小説というのはどんなものだろうと。
多重人格のパラノイアになるのは間違いないと思いますが(笑)。
とりあえず最初はラヴクラフトらし〜く始めてみました(笑)。
書き出しコメント・化夢宇留仁
1925年6月のボストン近くの小さな町でおこった事件は、新聞の片隅に小さな記事が載っただけでほとんどの人は気づかないか、気づいたとしてもすぐに忘れてしまっているであろう。
だが私はその事件のことを詳細に覚えている。 なぜなら私はその事件が起こる不吉な発端から、その劇的で忌まわしい終結までを望んでないにも関わらず、当事者としてその恐ろしい事件に関わっていたからだ。
新聞ではなんということはない事故として片づけれているが、この事件は断じて事故などというものでは無く、人為的なものでもないし、ましてや自然現象でもあり得ない。
実のところ、私もあれ以来のここ3年というものの、世間に知らせる事件の概要は新聞が伝えている程度でいいと思っていた。いやむしろそうするべきだと強く考えていた。そしてそれは今も変わらない。だがここ最近にいたって私の周囲に現れだしているあの事件の残滓とでも言うべき状況が、私に震える指でこの手記を書かせる必要性を感じさせた。
このままでは再びあの事件が発生してしまう可能性があり、しかもそれは次第に大きくなっているのが私には分かるのだ。しかも今度あの事件が起きてしまった場合、その規模は3年前とは比べものにならないほど巨大になっているであろうと予測されるのだ。
私にも想像も出来ない運命が迫っているのは明白だが、なにもかもが手遅れになる前にこの手記を残し、微細ではあるが少しでも状況を好転させる資料にしてもらえば光栄であり、やつらの導きにより地獄に堕ちるであろう私の魂にもわずかな慰めになろうというものである。
そもそもあれは私の古い友人のリチャードが、私の家にたずねてきたことから始まったのだ。
その時のリチャードは土気色の肌で、脂汗を流しながら震えており、目には魂に刻まれた恐怖が焼き付いているようだった。
昔の彼を知っている私には目の前にいるリチャードがとても本人とは思えず、何度も確認した上で、それでも信じられなかった・・・。
執筆・化夢宇留仁
「い、い、い、いもうとだよ、妹」
「妹?ヘラのことか?」
ヘラはリチャードの3つ離れた妹である。
幼少時、私とリチャードを加えた三人でよく遊んだものだが、彼女は兄の影
に寄り添うようで、まったく仲睦まじい兄妹であったように記憶している。
亜麻色の髪、伏し目がちな瞳、清潔な黒のブラウスからはかなげに伸びた その手足はビスクドールのようなきめ細かさである。まさにお人形というべき
可憐さであった。ひそかに思慕の情を抱いていた10歳の私は、
? 何を言っているんだ、私は? 「リチャード」の、「妹」だと?
「白い胸だ。…墓場の緑が。浅浮き彫りのオルゴールを隠したろ?
ヘラ、そんなつもりじゃ、(クククッ)なかったんだ、僕は、糸を」
リチャードは譫言のように妄言をくりかえすばかりで一行に要領を得ない。
傍目にも深刻な精神分裂の症状を呈しているのは瞭然であった。
「お、おい、落ち着けよ…妹、だって?」
執筆・@2c氏
私はアパートの玄関で意味にならない言葉をつぶやき続けるリチャードを、半ば力ずくでソファに腰掛けさせた。
彼の工員服からぼつぼつと滴り落ちる水がリビングの絨毯に染みをつくっていく。夕刻から降り始めた雨は勢いを増しているようだ。彼はこの雨の中傘もささずにここまで歩いて来たというのか。
私は秘蔵のブランデーをチェストから取り出すと、2つのグラスに半分ばかり注ぎ、そのひとつをリチャードの手に押しつけた。
「落ち着くんだリッチー。ほら、飲むんだ」
聞こえているのかいないのか、リチャードの反応はない。自分で一口飲んでみせる「ほら、こんな風に」
リチャードが魂の抜けた操り人形のように私の真似をする。と突然咳の発作に襲われた。
咳き込むリチャードの背中をさすってやりながら、私はヘラの事を思い出していた。亜麻色の髪…
リチャードは咳がおさまると多少は落ち着きを取り戻したように見えた。
「何があったか話してくれないか?ヘラがどうしたんだって?」
まだ学位こそ持っていなかったが、私は大学で心理学を学んでいた。分裂症の患者に好きなように話させてやるのが、そしてそれを聞いてやるのがいい影響を及ぼす事がある、ぐらいの知識はあった。たとえそれがどんなに馬鹿げた話であっても。
リチャードが口を開いた。
「…オルゴールの事を覚えているだろう」
私はうなずいた。オルゴール…確かに覚えている。 あれはもう10年も前になるだろうか。施設のクリスマスパーティで、慈善家から送られたプレゼント。それが偶然私のもらった箱の中から出てきた時、リチャードもヘラも目を輝かせた。リチャードは自分の貰った聖書と交換しようと言ったっけ。だが私は頑として拒否した。
リチャードは怒りと妬みの入り交じった視線で私を睨み付け、ヘラは哀しそうに小さく溜息をついた。
私は譲歩した。これを3人の宝物にしよう、と。
二人の友情を失うのが怖かった。特にヘラの。彼女への淡い恋情が結局そうさせてしまったのだ。
ヘラ…伏し目がちな瞳。私がそう言った時彼女の瞳は喜びに溢れていた。確かに。
「あれを教会の墓地に埋めただろう。ほら、カエデの木の根元に」
そうだ。3人で共有することになった宝物。しかしそれは私達の友情にまた新たな試練を与えた。誰が所持するのか?リチャードは常にその優先権を主張した。私達3人の中で彼はいつもリーダーだった。だが、違う。このオルゴールに関しては。誰かが優先権を主張できるとすればそれは私だ。オルゴールは私からヘラへの贈り物なのだ。私からのクリスマスプレゼント。初恋の人への初めての。
両親を失い施設で育てられた私には彼女へ捧げることのできる唯一のものだった。私はヘラに持っていて欲しかった。
だがリチャードは承服しなかった。私はここでもまた譲歩した。つまるところこれは3人のものなのだから、誰か一人が所持しているのは不公平だ。宝物は宝物らしく埋めてしまおう。教会のカエデの根元がいい。そして10年後に一緒に掘り出そう。3人の友情の証を。
私がそう言った時もまた、ヘラは嬉しそうに顔を輝かせていた。
ヘラ、清潔な黒のブラウスからはかなげに伸びた手足、ビスクドールのようなきめ細かな肌…10年後の今、君はどんな素敵な女性になっているだろう?
しかしヘラは存在しない。
リチャードは8歳の時に事故で両親を失った。彼は一人っ子だった。
引き取る親戚もいなかった彼は私と同じ施設にやってきた。
彼は友達もつくらず、いつも一人で物思いに耽っていた。そして友達がいないのは私も同様だった。
互いの孤独を埋め合わせるため私達は友人となり、…そしてある日彼は妹の「ヘラ」を紹介してくれた。それは私達二人だけの秘密の遊びだった。ヘラ、私達だけの想像上のひと。リチャードにとっては妹であり、私にとっては恋人…
私達がこの秘密の遊びをやめたのはいつだったろうか?
そうだ、オルゴールを埋めてそれから程なくだった。
ある日リチャードがこう言ったのだ。
『ヘラは南部の慈善家に養女として引き取られて行ったんだ』
そんな!私はその時の胸の痛みを思い出した。私はお別れさえ言えなかったではないか。もう一度、彼女に会いたい。会ってもう一度言葉を交わしたかった。あの亜麻色の髪、伏し目がちな…
「ヘラに会ったんだ」
私の物思いを破ってリチャードがぼつりとつぶやいた。
「えっ」
「10年目だよ。約束の10年目。…今日」
私は言葉を失った。
「ああっ、ヘラそんなつもりじゃなかったんだ」
リチャードは両手で顔を覆うと嗚咽の声を漏らした。
『ヘラ…』
窓の外では雨足が一層強くなっていた。
執筆・マッドハッター氏
リチャードの言動に、私の鼓動は激しく高まった。
そんなことはあり得ない。想像上の遊びでしかなかったヘラに、再会するなど不可能だ。
そもそも再会どころか、我々はヘラに会ったことさえないのだ。
リチャードは明らかな精神分裂症状を示しており、その言動がおかしいのも当然である。だから彼がどんなことを言い出そうが、私がショックを受ける理由はない。
だが、リチャードの言葉は私の胸を締めつけ、心臓は更に激しく鼓動を早めていた。
私とリチャードが穴の中のオルゴールに土をかけていたとき、振り返ると太陽を背に、ヘラが微笑みを浮かべて私たちを見ていた。
それは私たちの友情が永遠に続くのを心から喜んでいる微笑みに思えた。
私は自分の選択が正しかったことを確信し、誇らしいと同時に、日差しを受けて微笑んでいるヘラのことを心から好ましいと思ったのを覚えている。
違う。あり得ない。
これは記憶ではない。私がリチャードの話を聞いて、忘れていた記憶を呼び覚まされたために、その刺激によって脳がありもしない記憶を作り出したのだ。
絶対にあり得ない。
ではリチャードは誰に会ったというのだ?
私は深呼吸をしてなんとか落ち着きを取り戻した。
「リチャード。確かにオルゴールを埋めたのは10年前の今日だ。あれは君と私の友情の証だった。懐かしいな。」
「違う!」
リチャードが突然目を見開き、私に挑みかかった。
「僕のオルゴールは、君と、ヘラの為に!あのカエデの木の根本に埋めたんだ!」
恐ろしい形相だった。これ以上刺激してはならない。
それにしてもヘラのことはともかく、オルゴールまで自分の物だと宣言されたのには少し腹が立った。あれは私がヘラにプレゼントしたのだ。
「そうだったかな。なにしろ昔のことだからね。で、オルゴールは見つかったのかい?」
リチャードは大きく息をついて、再び顔を伏せた。次の声は元通りのつぶやき声になっていた。
「まだだ。まだ掘ってないさ。オルゴールを掘り出す前に、3人が揃わないと。だってそのために埋めたんじゃないか。」
言われてみればその通りだ。しかし3人揃うことはあり得ない。
彼女はもういないのだ。
彼女は南部の事業家に引き取られていったのだから。
違う。
そうじゃない。
彼女は最初から存在していなかったのだ。
だがリチャードは彼女に会ったと言った。会ったというのなら彼女は存在するのか?
また動悸が激しくなってきたので、あわてて深呼吸をした。
それも違う。彼女に会ったというのは彼の頭が生み出した幻想だ。
では私の記憶はなんなのだ?これも幻想だとしたら、私もリチャードと同じく精神に異常をきたしているのか?
確認してみなくてはならない。
「ヘラに会ったんだって?どこで会ったんだね?どんな様子だった?」
リチャードはしばらく呆然としているように見えたが、やがてつぶやくように答えた。
「どこで会ったって、決まってるじゃないか。カエデの木のところだよ。今日は3人が再会してオルゴールを掘り出す約束の日なんだから、あそこにいるに決まってるじゃないか。」
「そ・・・そうか。元気そうだったかい?」
「ヘラは・・・」
彼はまた呆然とした表情になり、次の瞬間には恐怖と絶望が入り混じった顔になり、再び涙を流した。
「ヘラ・・・すまない・・・そんな・・・そんなつもりじゃ・・・・」
だんだん分かってきた。彼は幻想のヘラと出会い、その彼女になにかをしたのだ。その結果
幻想に対して罪悪感が生まれる。
生み出された罪悪感は幻想に対するものだから罪滅ぼしも出来ずに、結果緊張しきった彼の精神を破壊したのだ。
私が彼のために出来ることはただ一つ。カエデの木のところに二人で行って、ヘラが存在しないことを証明するのだ。
そうすれば彼の罪悪感は消え、精神も行き場のない感情から開放されて、安定を取り戻すかも知れない。
私は泣き崩れる彼から視線を窓に移した。
外はまた雨足が強くなったようだった。
私の気分もその灰色の空に似て、ぼんやりとして曖昧な、どこか感情を置き忘れたような気分だった。
私が一緒にそこへ行くと言うと、リチャードは再び呆然となったが、すぐに弱々しく笑顔を浮かべた。
私は確信した。
やはりこの約束を果たすことが、彼の精神に好影響を及ぼすのだ。
リチャードは落ち着いてきたようで、眼にも少し知性の輝きを取り戻してきたように見えた。
ずぶ濡れの工員服を私の服に着替えるのにも素直に同意した。
やがて我々は雨の中、傘を片手にカエデの木のある場所に向かっていた。
その時私にはなにか予感があったのだろうか。
自分でも理由はよく分からないまま、懐には拳銃を忍ばせていた。
カエデの木は、小さい頃の記憶と変わらない姿でそこに立っていた。
しかし私のその場所の記憶はあいまいで、あらためてその場所に立った時、背筋が冷たくなり、心が恐怖にさらされるのを抑えることは出来なかった。
そこはうち捨てられた墓場だった。
雨にけぶる私の視界は、立ち並ぶ墓石と、不気味な納骨堂を認めた。
離れたところに見える教会はすでに使用されなくなって長い年月がたっているらしく、ところどころ朽ち果
てていた。
どの墓石も古いものばかりで、この墓場自体しばらく手入れもされていないように見受けられた。
件のカエデの木は納骨堂のすぐそばの開いた場所に、納骨堂のレンガ壁に寄り添うように立っていた。
次の瞬間、私は場所に対する恐怖など問題にならないものを目にしていた。
カエデの幹に隠れて、傘を差した若い女性らしき人影が立っているのに気付いたのだ。
私の心は張り裂け、恐怖を通り越した自己喪失感を感じていた。
自分が自分でないような、世界も現実ではなく、全てが悪夢の中の出来事のようだった。
そうだ。これは悪夢に違いない。
私はベッドの中で悪い夢を見ているのだ。
そうでなければ私は気が狂っているに違いない。
そうだったのだ。
狂っていたのはリチャードではなく、私の方だったのだ。
今頃私は自室のベッドの中ではなく、療養所の狭く汚いベッドの中で悪夢にうなされているに違いない。
だが、私の傘を持った手にあたる雨は確かに冷たかったし、墓場特有の臭気もはっきりと感じていた。
私の五感はこれが夢ではなく、現実だと告げていたのだ。
私が恐慌状態に陥り、口もきけない状態で立ち止まっている内、カエデの背後の女性はこちらの存在に気付いたらしく、振り向いてこっちに歩いてきた。
果たして陸に上がった魚のように口を開け閉めするしか出来ない私の前に、彼女は立った。
亜麻色の髪、伏し目がちな瞳、黒のスカートから伸びたビスクドールのような白い足。
彼女は、私が思い描いていた成長したヘラそのものだった。
私は意識が遠のいていくのを感じていたが、目の前のあり得ない現象は消えることなく、更に進展していった。
彼女は小さい頃のヘラそっくりのほほえみを浮かべて言った。
「さあ、私たちのオルゴールを掘り出しましょう。」
彼女がカエデの方を振り向くと、その木の幹の根本にはいつの間にか人が一人通
れるようなうろが出来ており、更にあり得ないことに、そこには地下に続く階段らしきものさえ見受けられた。
奥はどれだけの深さがあるのか、雨で視界はくもり、降りたすぐ先は暗闇になってなにも見えなかった。
ただ穴のそこかしこに、蜘蛛の巣を思わせるような白い糸が大量に付着しているのは確認できた。
茫然自失となり、なにが現実でなにが夢なのかも分からなくなった私が顔を上げると、カエデの木が雨にけぶってぼやけたシルエットになって見えていた。
そのシルエットは、その時ぼんやりと思い出したオルゴールの浅浮き彫りにそっくりだった。
執筆・化夢宇留仁
わたしはかろうじて踏みとどまった。
自らを奮い立たせ、改めて「ヘラ」をじっと見遣った。彼女は無邪気な微笑を浮かべながら、いささかの疑念を抱くこともなく、わたしの行動を見守っている。
降りしきる六月のなまぬるい雨が、傘から伝ってきて、靴の先に、じっとりと滴り落ちた。革靴を通
して染みわたり、わたしの爪先を濡らしていく、水、水、水の<透明な>感覚。どんよりとした墓場の空気と、奇妙な対照を為している。
リチャードと三人で、よく「水で遊んだ」ことを思い出した。後に、大学で思春期児童の行動と心理形成について学習した際、かつての体験を、悪夢とともに身につまされたものだ。二度と戻らない時間と取り返すことの適わない過去を前にして、自らの愚かしさを、心の底から悔やんだ。偽りのやすらぎ。若気の過ち。水遊びならぬ
、危険な火遊び。あれくらいの歳の子どもは、誰でも性的な欲動を抑えきれないものだと、年を空けたいまならば、自分たちの行動をいくらか正当化できはするのだが、かといって、開き直ったとしても、許されるものではあるまい。穢らわしく、忌まわしい、背徳と冒涜の縁に耽溺していたわれわれの、あのような、そう、あのような行為が……。
――どうして掘り出してくれないの?
――わたしたちの約束、忘れちゃったの?
郷愁と悔悟、憧憬と妄念とが入り交じった感傷に、「ヘラ」の透き通ったか細い声が畳みかけてくる。コトバが分裂し、深遠なる宇宙上を、辿り着く先も知らず、ひたすら舞い続けているかのようだ。私は文明人としての誇りを忘れ、親父の形見である、コルトM1917を握りしめた。いざとなれば、これでアタマを打ち抜くまでだ。そうすれば、すべてが終わりを迎え、安寧のときが訪れる。リチャードも、ヘラも、私も、皆が幸せになれ、かくて、物語は大団円と相成る。
しばしの沈黙。
「ヘラ」はじっと、わたしを見ている。
見つめ返す。その瞳には、確かにわたしの姿があった。
だが結局のところ、沈黙を打ち破ったのは、リチャードだった。狂水病のネズミのような勢いで、穴のなかに這い降り、手で土の中をまさぐった。
「あったァ、あったぞゥッ!!」
リチャードの狂気じみた声が響き渡る。が、その声はすぐに悲鳴に変わった。それを聴いて、わたしは呆然とした思考の宙づり状態から逃れさり、友を助けるべく、穴に駆け込んだ。
穴は血の海だった。
リチャードの両腕は噛み切られていた。ほとばしる鮮血のシャワーを浴びてわたしが観たものは、虹色に輝く悪夢じみた幾千もの眼であった。
大地が揺れはじめた。わたしは泣き叫ぶリチャードを必死で抱えて引きずりながら、穴の中から這いだし、走りはじめた。
そのときわたしは「ヘラ」を観た。
それはもはや、われわれの「ヘラ」ではなかった。
美しかった少女は、真珠母色に彩られた原形質の、不定型な泡の異様な集合体に変わっていた。緑がかった光を放つ何万ものイボが、斑点のように集まっており、それら一つ一つに眼球が備わっていた。そしてよく見ると、粘液に被われ、耐え難いまでの腐臭を放つその姿は、いまわれわれが出てきた穴のなかに居た<それ>と繋がっているかのようだった。知らず、かつてドラッグストアで購入したパルプ雑誌に載っていた、ペンギンを轢き潰す巨大なバケモノが思い出された。
わたしは戦慄し、全身の力が抜けていくかのような無力感を覚えた。が、一方で、信じられないほどの速さで銃を構えている自分に気がついた。
「こうなるべきだったし、こうであるべきだったんだ! わたしのヘラは!」
叫び、コルトを弾切れするまでぶっ放した。
失血多量で青ざめ、その場に倒れ込んで事切れる寸前だったリチャードが、わたしの様子を知ってか知らずか、なにかを、うわごとのように、繰り返し呟いていた。
「イエ、イエ、シュブ=ニグラス……」
リチャードの声は急に甲高くなった。
「幾千もの仔を孕んだ森の黒山羊よ!」
わたしは振り返った。
そこには巨大な雲上の塊が浮かび上がっていた。
納骨堂はすでに破壊されていた。
雲の一部はただれ、長い紐のような触手とチラチラ不気味にきらめく粘液、そして底知れぬ
深淵を思わせる裂けた大きな口と、何本もの鋭い牙とがあった。雲塊の下端には山羊を思わせる黒い蹄が映えていた。
大いなる母。強烈なる悪臭。
そしてその周りには、黒い覆面を被った何十人もの人間が集まり、奇妙な文句の詠唱をはじめていたのだった……。
執筆・Thorn氏
地獄がこの世に吹き出したようなそれを、私は知っていた。
論文作成のため、大学の図書館の保管庫まで入り込んで文献を探していたときに、ふと手に取った本があった。
それは単なる古い本にすぎなかったのだが、なぜか他とは違って見えた。まるで私を誘っているかのように感じたのだ。
パラパラとページをめくる内、その内容に夢中になってしまた私は、その日は結局その本だけを持ち帰り、その後1週間あまり読みふけって過ごしたのだ。おかげで論文は未完成のままである。
その本の中に、忌まわしき悪夢の産物としか思えない存在が暗示されていた。
シュブ・ニグラス。幾千もの仔を孕む森の黒山羊・・・
人類もまだ発生していない太古の昔からそれは存在し、悪夢を産み続け、人類が地上を闊歩するようになってからはその一部の人々にあがめられているという・・・
「イエ、イエ、シュブ=ニグラス」
そう。確かにあの本にはそのように書かれていた。
今私の前に、名状しがたい姿でそびえ立っているそれこそがシュブ・ニグラスそのものなのだと私は理解した。
またヘラの姿をとっていたおぞましい怪物のことも記されていた。
復讐の為に不定形の身体を絶えず変化させる恐るべき怪物ショゴスという名で。
雨の中、私を取り囲むように迫ってくる黒い覆面の男達は、例の詠唱を唱え続けていた。
恐怖と驚愕に取り込まれ、動くことも出来ない私に、詠唱がまとわりついた。声の強弱が波のように打ち寄せ、私を混沌の海に突き落とそうとしていた。
彼らの背後には、両腕から血を流したまま、薄笑いを浮かべているリチャードと、傘をさして立っているヘラの姿もあった。
さっきのおぞましい姿は幻覚だったのだろうか?ヘラは元の美しいヘラだった。
ただし彼女は全裸であり、そして笑っていた。それはまさしくあの日オルゴールに土をかけていた私を見つめていた微笑だったが、その身体には私が撃ち込んだ弾丸が開けた無惨な穴が開いており、おびただしい血を流していた。
彼女の微笑は次第に妖しく淫猥なものに変化し、私をあの冒涜的な悦楽の記憶にたちもどした。
やがて雨もどす黒い血となった。
私たちは母なるシュブ・ニグラスの母乳であるあらゆる疫病を媒介する黒い血の雨に抱かれていたのだ。
身体の力が抜けてゆくと共に、私の中で恐怖は歓喜に変わっていった。
私は自分の身体が精神と同じく形を無くして溶けてゆき、ヘラと混じり合い、一つになってゆくのを感じていた。
リチャードも、周りの黒い覆面の男達も一つになってゆく。
我々は還るのだ。一つになって大いなる母の元に。
こうなるべきだったし、こうであるべきだったのだ。
何人もの意識と記憶が混じり合っているようだった。
リチャードやヘラ・・・見も知らぬ人々・・・溶け合う意識の中には、まったく異質と思われるものも混じっていた。
それは遙かな太古に原始的な惑星に不時着した生物の記憶のようだった。想像も出来ない科学力をもったそれは、自分自身を現地でも生存可能なように改造を施した。彼が惑星に乗ってきた乗り物も、一部は機能が生きており、その能力との連携で、全てうまくいく筈だった。その乗り物はあのオルゴールに似ていた。
混沌とした意志の中で、生存と、種の保存に対する欲求が大きくなってゆき、次第に知性と言えるものはかすんでいった。
しかしそれも他の意識に混じって薄れていった。
あと少しで一つになれる・・・。
少し気になることがあった。右手が重いのだ。
もう形を無くしてどろどろに溶け合っているというのに、なぜ右手が重いなどと感じるのだろう?神経がまだ溶けきっていないのだろうか?
実に不快な感触だった。
右手の重さが気になって、完全に一つになれない・・・
この右手が。
銃声。
私の右手には、銃口から硝煙を漂わせているコルトが握られていた。さっき撃ち尽くしたはずなのになぜ?
目の前でヘラの声がした。
しかしそう思ったのは気のせいだったらしい。
顔を上げた私の前には、想像もしなかった化け物がのたうち回っていた。
私はその光景があまりに予測がつかず、驚くのさえ忘れてただ目を凝らしていた。
それは強いて言えば昆虫に似ているだろうか。しかしそれは人間ほども大きさがあり、また大きさ以外にも明らかに昆虫とは異なる特徴もいくつも備えていた。
本来頭があるべき場所には縦に裂けたように大きく穴が開いており、そこからは無数の触手がのびてうごめいていた。そこから泥の様な色の液体と、悲鳴じみた音をたてているところからすると口に近い器官らしい。
その周りからは木の枝を思わせる人間の腕ほどの長さの、細長くいくつもの間接を持った腕のようなものが10本以上ものび、先端のハサミのような部分からガチガチと音をたてている。
その内の数本の先端からは白く細い糸がのび、ぞっとすることに私の身体にからみついていた。節くれだった身体らしき部位
の背中側には動物の体毛のようにびっしりと触手が生え、内側からはムカデに似た無数の脚が生え、狂ったように宙を掻いていた。
その身体は後ろに長くのび、木の根のような色に変わりつつ背後の壁のぼんやりと発光しているあたりに消えていた。
そいつの胸?のあたりにはどうやら弾丸が命中したらしい傷があり、そいつの血らしい泥のような液体が吹き出ていた。
ここは地下らしい。奥の方から届くぼんやりとした光で、まわりは木の根が張りめぐらされたむき出しの土壁で、私はその壁のへこみに身体半分押し込まれたような状態らしい。
だんだん動きが緩慢になってゆく化け物の様子をもっと見ようと立ち上がろうとしたが、身体中に白い糸がからみついており、立ち上がるにはベトベトした糸の一部をほどかなければならなかった。
私が近寄った頃には化け物は痙攣するだけで、声もあげなくなっていた。
銃が暴発せず、私が意識を失ったままだったなら、今頃こいつの糸で蜘蛛の獲物のようにグルグル巻きにされて身動きもとれなくなっていたに違いない。
そう思ったのをきっかけに、ようやく恐怖が私の脳裏で表面化しはじめた。
いったい何が起こったのだ?
この化け物は実在するのか?
こいつは私をどうしようとしたのだ?
これは悪夢なのか?
ここはどこなんだ?
混乱と恐怖のあまり、私は頭をかかえて膝をついた。
曖昧な記憶が蘇ってくる。
私はリチャードに導かれ、ヘラに出会い、更に古い本で暗示されていた千の仔を孕む黒山羊、シュブ・ニグラスに・・・
おかしい。
リチャードとは誰のことだ?
よろよろと明かりに向かって進むと、この地下室の壁は木の根が張り巡らされており、それに隠れていくつもの人骨が放置されているのに気付いた。
人骨はどれも脚をそろえ、腕は縮こまらせている。ちょうどさっきのべたべたとした白い糸で縛り付けられればそうなるような体勢である。
比較的新しいと思える遺体にはまだグルグル巻きになっていた糸が残っているものがあり、遺体もまだ肉の付いたものもあった。
その中にほとんどミイラのような状態の、工員服を着た男の死体もあった。何年も前に死んだに違いないそれは、記憶にあるあの男に似ているような気がした。
ボロボロになってめくれている胸ポケットには、リチャードという縫いつけがあった。
私は恐怖でのどがからからになっていたが、歩調をゆるめずに進んだ。右手にはまだ1発しか撃っていないコルトが握られている。
さっきの怪物の胴体は、壁にあるとてつもなく太い木の根からのびていた。
やつはこの木の一部なのだ。
その脇には、長方形の棺に似た箱が置かれ、それと隣の木の根は何百本もの細かな触手めいたものでつながっていた。
更にその奧には崩れた煉瓦と土の山があり、何体もの人骨が半分埋まっているのが見えた。
納骨堂につながっているのだ。
やはりここはさっきまでいた墓場の地下なのだ。
その箱の天板には、水晶に似た不思議な物質を並べて模様が描かれていた。例のオルゴールの浅浮き彫りと同じものだ。
それらは色とりどりの淡い光を発し、不規則に点滅していた。この地下空洞の不可思議な光源はこれだったのだ。
私の思考は完全に混乱していたが、なぜかはっきりとそれが何かは理解できた。いやむしろ覚えていたと言った方が正しいのかもしれない。
食虫植物が甘い芳香を発して虫を呼び寄せるように、この機械が獲物を呼び寄せる餌を作っていたのだ。今まで取り込んだ獲物の記憶を利用して、新たな獲物の記憶に介入する・・・。
私はコルトをその箱に向けて、今度こそ弾倉が空になるまで撃ち込んだ。
箱の光は消え、各所から血のような液体が噴き出した。同時につながっていた触手が箱から引き抜かれ、大本の太い木の根の各部が縦に裂け、さっきの化け物と同じような悲鳴を上げて、泥のような液を流しながらのたうち始めた。
壁中に根を張っていた大木のうねりは、その空間のそこかしこで落盤を発生させた。
私はなんとか腕で頭を守ってうずくまるしかなかったが、やがて太い木の根のすぐ横から太陽の光が漏れているのに気付いた。落盤によって天井が崩れ落ちたのだろう。
私は動きも弱々しくなってきた木の根の横をなんとか登り、地上にたどり着いた。
私が出てきたのは、例のカエデの木の根本だった。しかしぼんやりと記憶にある階段付きの地下への穴などは見あたらず、シュブ・ニグラスも黒い覆面
の男達も、そしてリチャードという男もヘラという女性もいなかった。
空は曇っていた。雨が降っていたことを示す形跡は、地面に点々と残る水たまりだけだけで、それだけでは雨に降られていたのも現実だとは断言できなかった。
湿った何本もの太いロープをねじり合わせたような音がして、私はカエデの木の方をふり返った。
木、いや木に似た姿の化け物は、再び苦しげに身をよじり、全体から細かい触手を伸ばし、うごめかしていた。
大きく痙攣するような動きを見せたかと思うと、私の目の前でそれは大きく縦に裂け、その中から1cmほどの小さな黒いものを大量
に吐き出した。
狂ったような虫の羽音が吹き荒れ、その何匹かは私の顔や身体に当たって地面
に落ちた。
羽虫は無作為に飛ぶ方向を決めているかのようにそれぞれが関係のない方向に飛び回り、やがてみな私の視界から飛び去った。
地面に落ちた羽虫を見てみると、それは昆虫と言うよりも羽と触手の生えた種子のようなもので、今も触手と羽をうごめかしていた。
私はそれらをあわてて踏みつぶした。
木の残骸からは黒煙が立ち上り始め、すぐに火がついた。どうやら地下から燃えているらしく、火はあっという間に手がつけられないほど大きくなり、私はそれを呆然と見ているしかなかった。
私は確かに孤児院で育った。
しかし友達といえる人はいなかった。リチャードという友達もいなかった。もちろんヘラという少女も。
シュブ・ニグラスなどという悪夢の産物も、実際に存在しているのかどうかは知らないが、私が出会っていないのは間違いない。
漠然とだが、私に分かっているのはあの墓地に、遙か昔から食虫植物が昆虫を捕まえるように、人間を繋ぎ合わせた記憶を餌に捕まえて生きてきた化け物が存在したと言うことだけだ。
あれが植物だったのか、昆虫だったのか、知能を持っていたのかなど、疑問は残るが私には見当もつかない。
駄目だ。
もう嘘はつけない。
今嘘をついてしまえば本当に自分を見失ってしまう。
ヘラという少女は存在した。
孤児院の中で、幼い身で、同じく孤児院にいた男子児童達に、性的なおもちゃにされ、自殺したのだ。
私は止めようとした。
いや。違う。
それは私自身がそうだと思いこもうとして作り出した偽りの記憶だった。
彼女を陵辱して死に追いやった者達の中に私もいたのだ。
彼女は微笑んでなどいなかった。あの微笑みは後で私が想像の中で希望して作り上げたのだ。
今思い出しても胸が張り裂けそうになる。
私は彼女を殺したのだ。
あの忌まわしい本に記されていたショゴスという復讐に燃える怪物に彼女が変化したのは、私の罪の意識がそうさせたのかもしれない。
私はデスクの上の古いオルゴールを開いた。
名前は知らないが、聞き慣れたメロディーが流れた。
これはヘラが私にくれたものだった。
私の誕生日にヘラが少ない持ち物の中からプレゼントしてくれたのだ。
そのしばらくあとに、彼女は死んだ。
このオルゴールは表面が金属製で、ところどころ錆びていた。どこにもなんの模様もない。
私はオルゴールを閉めた。
外の雨音しか聞こえない静かな部屋で、私は目を閉じた。
はっきりしているのはあれで終わりではないと言うことだ。
大量に飛び立っていった羽虫が種子だとすれば、また同じような悪夢が、それもより大規模に発生する恐れがある。
あれからしばらくは、私はあの箱を完全に破壊したのだから、もう大丈夫だと自分に言い聞かせてきた。しかしあれをあの化け物が作ったのだとしたら、また作れないとは断言できない。
それでもなんとか日常生活を続ける内に、私もこのおぞましい記憶を忘れかけていた。
だがここ最近私は気がかりなものを見かけるようになった。
道で通り過ぎた男は、記憶にあるあの男に似ていた。
雨の日に通りの向こうを歩く黒いワンピースを来た女性も、記憶にあるような気がした。
私が気が狂っているのであれば、それでいい。
そうでなければ新たな恐怖がちゃくちゃくと迫っているという、私の強迫観念をどうすればいいのだろうか。
あの羽虫たちの内のどれだけが根を張り、再び餌を探し始めたのか、想像もつかない。
蓄えた記憶を使って。
今朝雨の中、資料を取りに行くためにボストンに出かけ、通りかかったあるアパートの入り口には、見覚えのある工員服を着た男が傘をさして立っていた。気になって見ていると、一瞬だけその男はこっちをふり返った。
男の顔は私のものだった。
私はなにもかもを放り出して家まで逃げ帰り、これを書きはじめたのだ。
今度あれがはじまったら3年前の程度の事件ですむとは思えない。
私の体験を誰かが読めば、少しでも事態の収拾に役立つかもしれない。または私の狂気が証明されるだけかもしれないが、それもまた望むところだ。
私はもう気が狂っているのか?誰か答えを教えてくれ。私の記憶は私には信用できない。
ノックの音がした。
憔悴しきった私が恐怖に震える声で誰かたずねると、ドアの向こうの声は応えた。
「突然たずねてすまない。リチャードだ。昔同じ孤児院にいた。覚えているかい?」
もちろん覚えている。
彼は孤児院で私の数少ない友達だったのだから。
ふと窓に目をやると、ガラスを伝う雨の雫が見覚えのあるカエデの木のような形に見えていた。
執筆・化夢宇留仁
化夢宇留仁あとがき
リレー小説&リレープロット掲示板のオリジナル作品第2弾です。
最初にもあるリレー小説を一人称で書いたらどうなるかということ。
またクトゥルフ神話の作品によくある過去の事件を語るというスタイルで、最後にいかに冒頭の設定に戻ってこれるかというのも興味深いところでした。
一人称の方は特に問題もなくいい感じだったと思います。
過去の事件を語るスタイルは・・・最初も最後も化夢宇留仁が書くことになってしまい、試みの結果
としてはもう一つ面白みに欠ける展開になってしまいましたが、これはこれで仕方がないでしょう。
でも過去の事件を語るというスタイルは、今後も色々なパターンを試してみたいと思います。
「カエデの木の下で」というタイトルは、このコーナーに移す時点で化夢宇留仁が考えました。基本的にはリレー執筆時のタイトルを使いたいと思っているのですが、流石に「一人称」はどうかと思ったので(笑)。
|