死のワナの地下迷宮
I・リビングストン著
 シチュエーションアイディアで一気に書いてそうな、リビングストンらしい作品。
シチュエーションアイディアで一気に書いてそうな、リビングストンらしい作品。
この本の冒険の舞台は、タイトルの通り地下迷宮である。 他と大きく違うのはその迷宮自体がゲームであると言う事だ。
元々ゲームブックなのに他となにが違うのかと言えば、要するに小説としての設定上でも、この迷宮は腕自慢が探検し、突破できるかを競う舞台になっているのだ。
ゲームの中にゲームがある入れ子構造になっている訳で、複雑なようだがそうではない。むしろ読者と主人公の視点が他の作品よりも近く、感情移入し易く出来ているのは見事である。
表紙は迷宮の奥で冒険者を待ち構えるブラッドビーストと言う怪物が緻密なタッチで描かれている。
これから立ち向かう迷宮の恐怖を伝えていていい感じだ。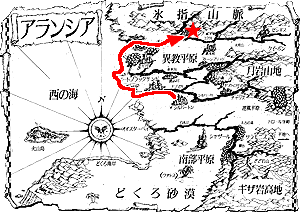
しかし、残念ながら彼ももう一つ印象が薄い。なぜならこの迷宮には、彼以外にも強力な怪物がいやと言うほど登場するのだ。
腕自慢の冒険者達を相手にする為用意された迷宮なのだから、仕方ないと言えなくも無いが、冒頭の遊び方のこつにある、「最初のサイコロの目がどんなに悪くても・・・」というのは信じがたい。
リビングストンは確率に弱いのだろうか?
しかし何より問題なのは、これ以降彼の作品が全般的にパワーゲームの要素が強くなっていったことである。その原因はこの「死のワナの地下迷宮」で強力なモンスターを出しすぎて、それ以降アクション映画の続編のように、もっと強く、もっと派手に、と求められるままに書いてしまったせいではないかと思う。それはそれで好みの問題もあるが、シリーズが進むにつれ、強いモンスターを出す事でゲームの山場が出来ていると勘違いしているような、一本調子の作品が増えていったのは残念なところだ。
本書自体はパワーゲームなところも設定上納得できるし、なかなか面白かった。
また新しい試みもいくつか成されている。
今までのシリーズでは、任務を負って出発した主人公の前にはまともな人間、または話しがまともに通
じるキャラクターは出てこなかった。たまに意気投合できそうな奴が出てきても、それはあくまで怪物であり、思考形態も想像のつかない怪物独自のものだった。本書では本当の意味でのキャラクターが初登場する。それは主人公と同じ迷宮への挑戦者の一人スロムと、迷宮の監督官であるドワーフである。
彼らには今までの登場人物には無かったものがある。それは不安を感じていると言う事だ。表すにしろ隠すにしろ、読者にはそれが伝わり、
彼らにはキャラクターとしての厚みを感じるのだ。このことは世界のリアリティを高めるのにも一役買っている。彼らの存在が、荒唐無稽な設定を生々しいものにしているのだ。
迷宮探検競技で盛り上がる町、ファングの存在も面白い。これといった産業もなく、さびれていた町を盛り上げる為にサカムビット卿がこの競技を発案したのだが、要するに村おこしである。
またゲームブック間に関わりがあり、同じ世界なのだとはっきりと明示したのは本書が初めである。
冒頭で主人公は盗賊都市ポート・ブラックサンドから船に乗ってファングへ向かうのだ。
いろいろな意味で記念すべき作品と言えるだろう。
蛇足だが、全体としてのゲーム性は大した物ではないが、本書のラストに出てくるパズルは面白かった。ある有名なパズルゲームそのままなのだが、シチュエーションとあいまって、どきどきさせる事請け合いである。
トカゲ王の島
I・リビングストン著
 またもやリビングストンの作品。
またもやリビングストンの作品。
彼は多作である。というよりもジャクソンが遅筆なのだが。
考えてみれば無理もない話である。必ず新しい試みを取り入れ、ゲームブック全体を通
してパズルとしても本としても高い完成度を目指すジャクソンが、ホイホイ作品を書き上げていたらそれこそ怪物だ。
などと書くとあたかもリビングストンの作品は完成度が低いと言っているようだが、そんな事はない。
彼の作品はストーリーと世界の描写に力を入れているが、作品全体を通したパズル性はあまり重視していない。したがって比較的短時間で完成度の高い作品に仕上げる事が出来るのだ。
「トカゲ王の島」もまさにそういう作品の一つだろう。
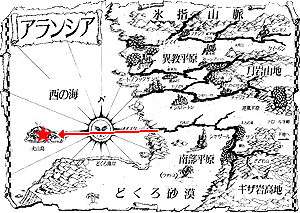 訳者(松坂健)あとがきにもあるが、本書はまさにレイダースばりの冒険活劇作品である。
訳者(松坂健)あとがきにもあるが、本書はまさにレイダースばりの冒険活劇作品である。
海を越え、ジャングルを進み、金鉱で戦い、呪術師の試練に耐え、悪しき王の砦へ開放された奴隷達と共に攻め込む・・・・・・・スター・ウォーズっぽくもあるな(笑)。
要するに冒険活劇の王道を行くストーリーなのだ。
ただし、ゲームブックとしては・・・・・・不満はないものの、手応え不足と言ったところだろう。
小説として活劇シーンの描写を読む限りワクワクする事請け合いなのだが、それに見合ったゲームブックとしての面
白さに欠けているのだ。
アクション映画がジェットコースタームービーとか言われるように、この作品もゲーム部分でテンポを崩さないように作られているのだと考えれば、まだ納得が行くが。
前記「死のワナの地下迷宮」でも触れたが、この作品でもポート・ブラックサンドが冒頭で語られる。さらに主人公はファングから旅をしてきたという事になっている。どうやら世界を共通すると共に、主人公も同一人物のようだ。だがそれははっきりとは書かれていない。ただそうなってもおかしくないという程度だ。
この辺の読者の想像を防がないバランス感覚は、シリーズを通していい感じである。
サソリ沼の迷路
S・ジャクソン(米)著
 スティーブ・ジャクソンの作品。ややこしいが、このジャクソンは今まで登場したジャクソンとは別
人である。
スティーブ・ジャクソンの作品。ややこしいが、このジャクソンは今まで登場したジャクソンとは別
人である。
この作品を書いたのは、カーウォーズやガープスシリーズと言えばご存知の方もあろう、アメリカのスティーブ・ジャクソンである。
ちなみに今まで出てきたジャクソンとリビングストンはイギリス人である。
一人でも出来るRPGを作ろうとして、お金のあるアメリカ人はコンピュータRPGを作り、お金が無かったイギリス人はゲームブックを作ったと言う話がある。
真偽のほどは確かではないが、なんか御国柄を感じて面白い。
さて、この作品だが、コンピュータ好き(?)のアメリカ人らしく、ゲームブックであるにもかかわらず、どこかコンピュータゲームのような感じである。
まずMAPが正確に書ける。というか最初から地図を書くことを前程にしている。さらに今までのゲームブックではほとんど不可能だった前に来た場所に戻るのが完全に出来る。スタート地点から沼の最深部まで行って、またスタート地点に戻ってくることさえ出来るのだ。まるでコンピュータRPGのウィザードリィみたいである。
回復の泉なんかもあって、ますますそれっぽい。
この構成は読者の想像力にも影響する。
化夢宇留仁はゲームブックを読んでいる時は、あくまで主人公の視点で画面を想像しているが、この作品に限っては途中から斜め上か20メートルくらいから見下ろした画面
に切り替わってしまった。しかも空き地には番号が・・・・(作品内でそれぞれの空き地に番号が設定されている)。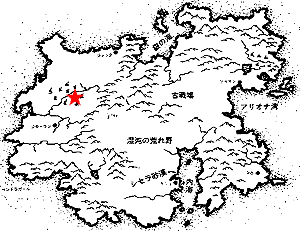
ま、こういうのもたまには面白い。
問題はタイトルになっているサソリ沼自体である。
上の説明にあるようにこの作品では同じところに何度でも来ることが出来る。といいう事は一つの場所に、少なくとも最初に入った時と、2回目以降に入った時と、
さらに入った方向関係無しに分かれ道を説明するためと、最低でも3つのパラグラフを消費することになる。
さらに作中では主人公は善、悪、中立のどれかの魔法使いに使えており、迷路内でもそれによって状況が変化する。つまりこれによってもパラグラフが消費されているのだ。
結果は明白。 迷路になっているのは確かだが、なんか小規模で、何人もの冒険者が挑戦して命を落とした恐ろしい場所とは到底思えなくなっているのだ。
これはパラグラフ数400というルールで作っていたらしいこのシリーズでは仕方が無いとも言えるが、これだけシステム面
に凝っていることを考えると、残念である。どうせならこれをプロトタイプとして、別
に同じシステムでパラグラフ数1000くらいの作品を書いてくれたらよかったのに・・・・・・・
前記に少しあるが、この作品では主人公は3人の魔法使いのうち、どれか一人の依頼を聞いて沼地へ出かけることになる。
実はそれらを無視して出かけることも出来るのだが、傷ついて戻ってくるか、デッドエンドが待っているのだ。
この3人の魔法使いだが、3人とも実にいいキャラクターである。
善の魔法使いはどうしても農夫にしか見えない毛深いおやじだし、悪の魔法使いはなんかせこいし、中立は商売人・・・・3人とも妙に味があって、とても楽しい。 ぜひとも続編を書いて、この3人にも登場してほしい。
沼には「あるじ」と呼ばれる魔法使いの集団がいる。彼らは狼や鳥など、特有のシンボルを持ち、そのシンボルに応じた能力を持っているようだが、結局最後までよく分からない連中だった。これも続編を書いて正体を明かしてほしいものだ。
ところで、地図を見てお気付きと思うが、この作品は初のアランシア以外の大陸クールを舞台にしている。だがこれはどうやら本書が書かれた後で決まったことのようだ。なぜなら本書の中で、主人公が張ったりとしてファングのサカムビット公の命により、モンスターを探していると話すシーンがあるのだ。いくらサカムビット公が力を持っているとはいえ、違う大陸まで手を伸ばしていたとは考えづらい。多分本書を書いている時点ではなんとなくアランシアのどこか・・・・と考えていたのだろう。
無理矢理考えればそういう噂だけは海を越えていたとも考えられるが・・・・・そういえば「死のワナの地下迷宮」には、どう見ても八幡国の忍者としか見えない奴が登場していた。もしかしたら交流があったのだろうか・・・?謎である。
雪の魔女の洞窟
I・リビングストン著
 何と言ったらいいのか・・・言葉が浮かばないが、いろいろな意味で記念すべき作品なのは間違いない。
何と言ったらいいのか・・・言葉が浮かばないが、いろいろな意味で記念すべき作品なのは間違いない。
リビングストンがアランシアを満喫した作品、 それが「雪の魔女の洞窟」である。
まずは右下の地図を見ていただきたい。
なんかもう目茶苦茶である(笑)。
というのも、この作品は元々英国のウォーロック誌に200パラグラフのショートゲームブックとして掲載されたもので、後の200パラグラフは今までのFFシリーズに出てきたアランシア世界を縦横に巡る冒険が、付け足して書かれたものなのだ。
最初に書かれた冒険は、アランシア北部の氷指山脈を舞台に、凍りついた洞窟を探検し、雪の魔女を倒すという内容である。
右の地図でいえば左上の星印がそうである。
ここまでは舞台が珍しいだけで、他に取りたてて変わったところのないいかにもなゲームブックである。ショートシナリオだからか、妙に前触れのないデッドエンドが多く、今回戦闘と運試しは成功したものとしてやり直したのだが、この前半部分でも何人か死者が出た。
あと特徴と言えるのは雪の魔女のキャラクターくらいか。
彼女は一言で言えば、わがままである。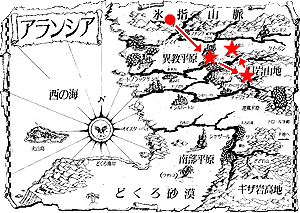
悪いやつというのはだいたいわがままなものだが、彼女の場合は無計画で、その上わがままなのだ。
例えばよくある展開で、「おろか者め!そんな約束は知ったことではないわ!」などと悪者が言ったりする。これもまぁわがままと言えなくもないが、この場合は計画的に嘘をついている。悪いやつが嘘をつくというのは、悪に勤しんでいるわけで、逆に言えば正直なのだ。
だが雪の魔女はそうではない。何事も行き当たりばったりなのだ。
ゲームをやって勝ったら出口を教えてやろうと言い、どんなゲームかと思えば、これから考えるとくる。
考えている間にこいつらの相手をしろと言われ、ゾンビと戦って倒したら残念がる。
ゲームが始まって、一度目にドローになると、悔しがってルールを変更する。
しまいに正々堂々と死んだかと思えば、呪いを掛けてくる・・・・・。
初の女性悪役ということで、リビングストンもそれを表現するのに力を入れたのだろうが・・・・面
白い(笑)。いい感じである。
さて、雪の魔女を倒した主人公は、そこで奴隷にされていたエルフの赤速とドワーフのスタブと共に、スタブの故郷であるストーンブリッジに向かう。
地図の丸印がストーン・ブリッジだ。
この先にまだ矢印が伸びているのからもお分かりのように、この本の後半はアランシア北東部を巡り歩く、今までにない展開なのだ。
これまでシリーズを通して読んできた読者にはおなじみの場所が次々に登場するこの展開は、まさにアランシア世界の水戸黄門、いや、アランシア世界がゲームブックに登場する場面だけでなく、独自に存在しているのだというアピールだと受け取れる。
これはリビングストンがそれを望み、今後の展開の起爆剤にしたかったということと、彼本人がアランシア世界を楽しみだしたということだと思う。その結果、後半の展開はまとまりを欠き、ゲームブックとしては首をひねらざるを得ないものになっている。
ただしそれはあくまでゲームブックとしてのこと。
今回やり直した感じでは、アランシア世界の物見雄山の体で、なかなか楽しめた(ルール通りプレイしていると、主人公は呪いによってじわじわと死が近づいており、とてもじゃないがそんな余裕は持てないのだが)。
また今までになかった世界の構築法の一つに、時間の概念がある。
とうとう作品間での時間的順番が明示されたのだ。
今までそれを匂わせはしたものの、はっきりとは書かれなかったこの要素は、あくまでそれぞれ単品の作品としての完成度を重く見ていた結果だと思うが、ここに来てとうとう世界の描写がそれに打ち勝ったと言えるだろう。
ちなみにそれはストーンブリッジで起こる。
ドワーフのスタブは、そこで村の命運を左右する魔法のハンマーが盗まれたと知り、それを探すべく友人のドワーフ、大足(ビッグレッグ)と共に探求の旅に出るのだ。
「運命の森」をプレイされた方には分かるだろうが、この事件は「運命の森」の冒頭部分の展開に繋がる。
旅に出た彼らは、ハンマーがダークウッドの森にあるという情報は掴んだものの、力尽き、最後の生き残りであるビッグレッグが、負傷により正気を失いながらもその意志を伝えるというのが、「運命の森」の冒頭部分なのだ。
要するに「雪の魔女の洞窟」は、「運命の森」の過去の事件だと書かれているわけだ。
これは大事件である。
この瞬間に、タイタンはゲームブックの舞台というだけでなく、一人歩きする世界として産声を上げたのだ。
ちなみにこの作品をプレイする上で、注意してもらいたいことがある。
それはこのシリーズの中で、最初に手をつけてはいけないということだ。
これは今までの説明文を読んでもらえば予想はつくと思うが、作者は明らかに本シリーズの読者サービスという意味合いも込めて作品後半を書いている。したがって最初に手をつけてしまうと、面白さの半分も伝わらないのだ。
もう一つの原因は、すごく死にやすいということだ。
化夢宇留仁は雪の魔女を倒してからも、戦闘と運試しは無条件で成功というルールで読み直していたのだが、それでも数回のデッドエンドを迎えた。
世界の表現に力を入れる余りそうなったのかどうかは定かではないが、とにかく死にやすい。
呪いにかかっている主人公は歩いているだけで体力点が減ってゆくし、敵も強い。呪いを解くための道筋は細くつらいものだ。
これは世界に馴染みがないとやり直す気にもならないかもしれない。
もう一度書いておくが、決してこの作品を最初にプレイしてはいけない。ただつらいだけである。
地獄の館
S・ジャクソン著
 新たなジャンルに果
敢に挑戦しつづける、スティーブ・ジャクソンの作品。
新たなジャンルに果
敢に挑戦しつづける、スティーブ・ジャクソンの作品。
この作品も「さまよえる宇宙船」と同じくタイタン世界を舞台にしているわけではない。
舞台は近代〜現代のアメリカ。
森の中、雨の夜道を走る主人公の乗った車が、エンコしてしまい、たどり着いた気味の悪い古びた洋館(アメリカだから当たり前/笑)・・・と、要するにホラーゲームブックなのだ。
設定からしてそうなのだが、例によって付け加えられた専用ルール、恐怖点(怖い目に合うと加算され、一定の数値になると気が狂ってしまってゲームオーバー)の存在など「クトゥルフの呼び声」を彷彿とさせる。
・・・・で、難度の高いものの多いジャクソンの作品の中でも一番難しいのでは?と言われている本作品。
訳者の安田均氏も、恐怖点は使わなくてもいいと言ったり、白地図を載せてみたりと、難度に対するフォローを行っているくらいである。
勿論化夢宇留仁はクリアしていない(汗)。
そういうわけで、これ以上は書きようが無い(汗)。
近いうちにプレイして、「何人死んだら気が済むの!?」 への掲載も考えているので、クリアするなり進展するなりしたらまた続きを書こうと思う。
NEXT
TOP
HOME
 シチュエーションアイディアで一気に書いてそうな、リビングストンらしい作品。
シチュエーションアイディアで一気に書いてそうな、リビングストンらしい作品。
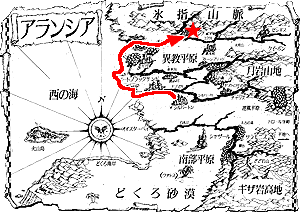
 またもやリビングストンの作品。
またもやリビングストンの作品。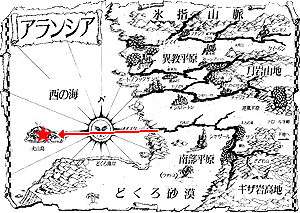 訳者(松坂健)あとがきにもあるが、本書はまさにレイダースばりの冒険活劇作品である。
訳者(松坂健)あとがきにもあるが、本書はまさにレイダースばりの冒険活劇作品である。 スティーブ・ジャクソンの作品。ややこしいが、このジャクソンは今まで登場したジャクソンとは別
人である。
スティーブ・ジャクソンの作品。ややこしいが、このジャクソンは今まで登場したジャクソンとは別
人である。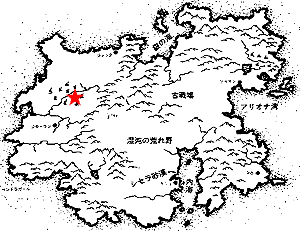
 何と言ったらいいのか・・・言葉が浮かばないが、いろいろな意味で記念すべき作品なのは間違いない。
何と言ったらいいのか・・・言葉が浮かばないが、いろいろな意味で記念すべき作品なのは間違いない。
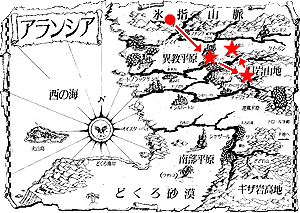
 新たなジャンルに果
敢に挑戦しつづける、スティーブ・ジャクソンの作品。
新たなジャンルに果
敢に挑戦しつづける、スティーブ・ジャクソンの作品。