宇宙船シナノマルの人々
第4回
密航者
翌朝、出航準備が整った。 ルシアがエンジニアの経験があるということで、パワープラント、並びにノーマルドライブの点火を担当したが、これが非常に手間取った。
パワーは上がり、船内に力強いハム音が響き始めるのだが、いざ点火となるとなぜか尻つぼみに音がパワーが下がり、やり直しになってしまう。
彼女は何度も謝って必死にやり直していたが、出航できたのは予定よりも2時間も後だった。
船は徹底的にメンテナンスされているはずである。なにしろ購入したばかりなのだ。つまりエンジンがかからない原因は彼女にあるということである。
雇い主であるローバンは船長席にふんぞり返ったまま黙っていたが、指は忙しく肘掛けを叩いていた。
その後ジャンプ可能域に達し、ジャンプの作業に入っても彼女が謝る声はブリッジに何度も聞こえていた。
ローバンはすでに自室に引っ込んでしまっていた。
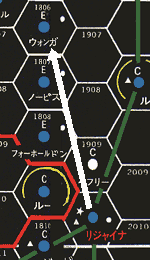 そんなこんなで貴族と3人の付き人と4人の操船担当者を乗せたY型ヨットは、なんとかウォンガへ向けてジャンプに入った。
そんなこんなで貴族と3人の付き人と4人の操船担当者を乗せたY型ヨットは、なんとかウォンガへ向けてジャンプに入った。
ジャンプ空間では外部の様子はまったく変化無く、進んでいるのか止まっていいるのかさえ分からない。 もちろん外部との連絡は全く取れず、船は完全に孤立した状態となる。
宇宙ではあなたの悲鳴は誰にも聞こえない・・・のだ。
ジャンプ突入時、ブリッジには操舵席にチーク、副操縦席にロビン、通信士席にマービンが座っていた。
なんとかジャンプ空間に安定し、仕事の最初の山場は越えたとほっとする3人だが(もちろん機関室ではルシアもほっとしているであろう。)、いきなりマービンの前のコンソールの一部が点滅し、警告音が鳴り響いた。
あわてて確認すると、食料貯蔵室の中に異変がおきていた。
表示されたデータは、貯蔵室のドアが内部からの圧力を感知していることを示していた。
内部からの圧力? ガスでも発生したのだろうか?
しかし内部大気は正常値を示している。
「どうした?」
思わずロビンが海軍士官の口調で問いただす。
マービンが状況を説明すると、ロビンも首を傾げた。
ロビンが考えるときの癖らしく、自分の顎をいじりながら聞いた。
「温度に変化は?」
マービンがあわてて確認する。
「現在チルド保存モードに移行が完了したところで、庫内大気が6.5度c。各パッケージ内は4度c。異常は無いです。」
「圧力の数値は?」
「数値が変化してますが・・・5から10kg程度。断続的に発生しています。」
「断続的・・・」
ロビンがさらに考え込む。
チークが操舵席から立ち上がった。つかつかとブリッジ内の緊急ロッカーに歩み寄ったが、ロックがかかっているようでロッカーは開かない。
「ちくしょう。オーナーからすれば俺たちも信用できないんだろうな。」
「どうした?なにをしようとしてるんだ?」
「知れたこと。武器を出そうとしてるのよ。」
「武器?どうするつもりだ?」
チークはロッカーをけとばしてから振り返った。
「あんたらお上品な船にしか乗ったことが無いようだな。貯蔵室のドアに断続的な圧力といったら、寒さに耐えきれなくなった密航者が暴れてるのに決まってるだろうが。」
ロビンとマービンは二人ともぽっかりと口を開けてうなずいた。
結局ローバンに状況を報告し、検討の結果チークとマービン、それに話を聞いて志願したルシアが確認しに行き、他は全員ブリッジで待機することになった。
マービンとルシアは自分のライフルを持っていたが、船内で使うには強力すぎたので、全員船内ロッカーから出したカービンを装備した。
ヨットは大きく上下に3層に分かれていた。ブリッジは第2層の先端にあり、船室横の通
路を通ってエレベーターで第3層に下り、船倉のドアを横切った先に貯蔵室のドアがあった。
貯蔵室前に来ると、予想していたドアを叩く音はやんでおり、静かだった。
チークとルシアはこういう状況に慣れているのか(慣れていたのだ)、テキパキと動き、チークが指示を出してルシアとマービンが貯蔵室のドアの左右についた。
マービンは銃の扱いには慣れていたが、それはあくまでハンターとしてのこと。こんな市街戦のような状況ではどうしていいか分からなかった。
チークは肩に研究所で借りてきたビデオカメラを固定して、撮影していた。
ブリッジでは残ったメンバーが送られてくる映像に固唾をのんでいた。
ロビンが小声で通信機に向かって話す。
「状況は確認した。こっちもいつでもアンチハイジャックモードに入れる。そちらの準備でき次第行動してくれ。」
「了解」
チークのささやき声が返ってきた。
チークが右手を小さく振った。 ルシアが黙ってうなずき、貯蔵室のドアの開閉スイッチを操作した。
同時に全員カービンをドアに向けた。
ドアの大型ノブが自動的に回転し、開放される。
冷たい空気が流れ出、同時に中から人影が力無く通路に倒れ込んだ。 3人の銃口はその動きに合わせて下がった。
マービンは倒れているのが女性だと気づいた。
長髪を後ろでくくり、宇宙服でもなんでもない普通の薄汚れた服装だった。
 女性は倒れたまま動かない。マービンが駆け寄ろうとするとチークが叫んだ。
女性は倒れたまま動かない。マービンが駆け寄ろうとするとチークが叫んだ。
「待て!動くな。」
マービンを止めておいて、チークがゆっくりと近寄ってゆく。
「少しでも妙な動きをしたら射殺する。意識があるなら返事しろ!」
「そんな無理でしょ・・・」
マービンが話そうとするが、やはりチークが腕で制止の合図をしたので黙った。
女性はもぞもぞと動き、「あ・・・寒い・・・」とうめくようにつぶやいた。
「よしまず両手を見せろ!」
少し間があって、女性が身体の下に隠れていた両手を出した。なにも持ってはいないようだ。
「よし!拘束!」
マービンが唖然として見ている間に、チークとルシアが完全に無駄のない動きで女性をうつぶせにひっくりがえし、後ろ手に用意してきた手錠をはめた。
チークが身体検査をしようとしたが、ルシアににらまれて引き下がった。
ルシアが調べたところ、女性はこれといった所持品は無かった。
「しけてるな・・・」
チークがつぶやく。
「そうね。」
ルシアが無意識に応えていた。
マービンはただ呆然とそれを見ているだけである。
それにしてもこの状況でなにがしけてるのだろう?
チークが通信機に報告を始めた。
「密航者を1名確保。女だ。所持品なし。これから貯蔵室内を確認する。」
「了解」
ルシアが女性につき、チークとマービンの二人で貯蔵室に入った。
中は寒く、息が白く見えた。確かにこれでドアが閉まっていたらたまったものではない。
すぐに破られた大型パッケージと、ぼろい旅行鞄が見つかった。
どうやらパッケージに入ろうとしたらしい。
中には食料が詰まっている上に室温よりももっと温度が低いというのに。
通路に出て鞄の中を確認する。
着替えと記録用クリスタルがいくつかと、現金が85クレジット入っていた。 身分証らしき物はなにもない。
チークがまた報告する。
「旅行鞄を発見。特にめぼしい物なし。これから処理にはいる。」
そう言いながら女性の両脇に手を入れて半分持ち上げた。
「マービン、手伝ってくれ。」
そう言って足の方を顎で指示した。 マービンが足を持ちあげると、チークが移動を始めた。
「ルシアさんはクリスタルと金をよけて鞄を持ってきてくれ。」
「はいはい。」
ルシアも手慣れた様子である。
船室に連れて行くのかな?そうマービンが思ったところで、ブリッジからの返信があった。
「処理・・・というのはどういうことかね?医務室に連れてくのか?確かマービンくんが1レベルの医学ライセンスを持っていたな。」
マービンのそれはもちろんハンターとしての現場の対処のためのものである。
しかしチークは首を振った。
「いやいや単に捨てる準備をするんですよ。安心してください。クリスタルと金はとっときますから。」
しばらく返信がなかった。
マービンも少し混乱して思考がまとまらなかった。
たどり着いたのは空いてる船室の一つだったが、部家に入るとそのままバスルームに直行したので驚いた。
そこでやっとブリッジから返信があった。
「ちょっと待て。捨てるというのは船外投棄のことか!?」
「いやいやジャンプ中ですよ。そんなことするわけないじゃないですか。今はしめるだけですよ。しめたら冷凍室に放りこんどきますから、ジャンプアウトしたら捨てましょう。」
チークが自分のベルトを外し、女性の首に掛け始めたのを見てはじめてマービンはなにをしようとしているのか分かった。
あわててルシアに振り返るが、彼女はにっこり笑みを返してきたのでこれまた驚いた。
「待て!よせ!やめろ!」
通信機からロビンの叫び声が聞こえた。
マービンもチークの腕に飛びついた。
「なんだなんだ。なにがどうした!?」
当のチークもまた驚いているようだった。
約1時間後、船体中央上部にあるガラス張りの豪華な展望ラウンジでローバンが怒っていた。
「いったいどういうことかね。私の船で殺人事件を起こすつもりだったのか!?」
「いやいやいやそういうことではなくて。ローバンさんはこういう状況は初めてのようですが、密航者ってのは人間じゃないんです。生かしておいたらいざというとき食料その他が足りなくなって、全員の生命の危機を招きます。ですからあくまで余剰物として扱うことになってるわけです。」
「しかし彼女は生きてるぞ。しかも私の船だ。」
「しかしこれが宇宙のルールってもので・・・」
「まあ待てよ。チーク。」
ロビンが割って入った。
「確かにそれはそういうルールになってるが、あくまで建前だろう?物資も燃料も余裕のあるこの状況で、普通 いきなり処理はないだろう。」
「そうですか?それが当たり前だと思ってましたが。」
「そんなことが当たり前だったのはもう1000年も前のことだろう。零細自由貿易船や海賊とかならあるかも知れないが・・・」
「へっ」
チークが黙った。
確かに今彼が常識と言ったのは海賊時代の経験が元である。
そうか普通の船ではさっさと処理はしないのだ・・・。
彼にとってそっちの方が新鮮な驚きだった。
「あ〜・・・そうですね。ちょっと時代錯誤でしたか。はははははは」
笑ってごまかすことにした。
そこにルシアが入ってきた。
「女性の意識が戻りました。名前はリーナ・アッバープと名乗ってます。なんだか親戚 にお金を借りるために乗り込んだとか・・・・でもどうして処理しないんですか?余剰物ですよね?」
にこにこしているルシアだったが、ラウンジ内は静まりかえっていた。
船室では一応医学ライセンスのあるマービンがリーナについていた。
彼女は年齢27歳、疲れたような表情と、薄汚れた服・・・・お金を借りに行くというのはほんとうだろう。
船倉に医療キットをとりに行っていたエイビーが戻ってきた。
「これでいいですか?」
「ありがとう。でもどうやら使わなくてもすみそうです。単なる栄養失調と寒さによる疲労でしょう。」
「そうですか・・・」
なんだか腑に落ちない顔をしている。
「どうしたんです?なにか問題が?」
「あ、いやすみません。関係ないことなんですが、ちょっと気になることが・・・」
「と言うと?」
「今船倉でですね・・・人影を見たような気がしたんですよ。」
「BさんかCさんでは?」
「違うようなんです・・・それに足跡のようなものが・・・しかも小さくて、子供のもののようなんです。」
「・・・・・・」
再びカービンを構えた3人が、今度は船倉へ出撃した。
武装して展望ラウンジ横の螺旋階段をいそがしく下りてゆく3人は、まるで軍隊そのままな雰囲気である。
ほとんど荷物らしい荷物も積んでない船倉の片隅の断衝ケースの陰にそれはいた。
3つの銃口を向けられ、泣きながら手を挙げたのは金髪をマッシュルームカットにした小柄な少年だった。
また展望ラウンジでローバンが怒っていた。
「いったいどういうことだ!?リジャイナ宙港は誰でもフリーパスで行き来できるのか!?」
「まあまあ、我々が自由に入れるように係官に言付けしておいてくれたではないですか。そこに隙があったようですな。」
ロビンがとりなす。
「それにしても一度の航海に関係ない密航者が2人も紛れ込むとは・・・こんなことあり得るのかね?」
「私の経験では初めてですな。」
当の少年もテーブルについてふくれていた。
「大人はやだね。何事も慣例が無いと対処できないんだよね。」
二人のおやじににらみつけられたが、彼はぷいと目をそらした。
「かわいげのないガキだ。こんなやつならチークくんの方法に賛成したくなるよ。」
ローバンのセリフにロビンもうなずいた。
「まったくです。だいたい船倉は通常航海中は真空にする場合が多い。君は本来ならあそこで死んでたんだぞ。」
「こうやって生きてるじゃないか。説教なんか聞きたくないね。」
おやじ二人が腰を浮かせたが、付き人たちがなんとか制止した。
それまで黙って珈琲を飲んでいたチークが口を開いた。
「ま、オーナーのお望みならすぐにでも処分しますがね、しかしこいつは生かしておいた方がいいでしょう。」
「ほう。なぜだね?余剰物じゃないのかね?」
「このガキの身なりはさっきの女と違って金持ちのものです。多分いいとこのボンボンでしょう。生かしておいたら礼がもらえるかも・・・」
そこまで言ってローバンが貴族だったと思いだした。
「礼など必要なくても、親は心配して探してるでしょうから、ちゃんと返してやらないと問題が生じるかも知れません。」
「なるほど。それはそうだ。で、こいつの名前は・・・」
「ラヴィカン・ストーロというそうです。しかしそれ以上なにも言おうとしません。私に任せてもらえるなら吐かせて見せますが?」
「・・・いや、よそう。」
まったくチークに任せておいたら子供でもなにをするか分かったものではない。
当の本人はひたすら無視を決め込み、だされたケーキを不味そうにつっついていた。
「なにか面白いビデオでもないの?ボク血しぶきが出てくるやつが好きだな。」
おまえを血だるまにしてやろうかい!などと3人は考えていた。
機関室にチェックに行っていたルシアが戻ってきた。
「チェック完了しました。どうやらどこもいじられてはいないようです。」
「よかったよかった。これでジャンプドライブにいたずらでもされてたら目も当てられない。さ、君もコーヒーでも飲んで休みたまえ。」
「あ、ありがとうございます。でもちょっと機関室に工具を忘れてきてしまって・・・すぐとってきますので。」
「それにはおよばんよ。シーガル」
ローバンの呼びかけに、すぐに付き人のシーガルが出てきた。
「ルシアさんが機関室に工具を忘れてきたらしい。取ってきてやってくれ。」
「はい。」
「あらあら私自分で行きましたのに。」
「いやいや、君は出航以来働きづめだ。少しゆっくりしたまえ。」
「ありがとうございます〜」
こうしていきなりの密航者騒ぎも一段落したかに見えた。
コーヒーを飲んで一息ついた頃、ルシアはラウンジの隅でエイビーとビートがなにやら困った顔をして話し合っているのに気付いた。
「どうしたんですの?」
「あ、すみません。クリモアさんの工具をとりに行ったシーガルがまだ戻らないんです。コールしても返事してこないし・・・」
あれから15分はたっている。ヨットはそんなに広いわけではない。
「工具なら別に急ぐ物じゃないからかまわないですよ。」
「はいありがとうございます。しかしそれにしても連絡もないのはおかしい。私が見てこようと思います。」
「私も行きますわ。」
ルシアも同行し、機関室へ。
螺旋階段を下りて第2層へ。ここの最後尾が機関室である。
機関室に繋がる談話室のドアを開けると、向かいの機関室のドアが開いたままになっているのが見えた。
物音はなにもせず、ただパワープラントのハム音と、床下からはジャンプドライブの高音の混じった動作音が響いているだけである。
「シーガル、どこだ?」
エイビーが声をかけたが返事はない。 彼は気にもとめていなかったが、ルシアはなにか禍々しい空気が漂っているのを感じていた。
「シーガ・・・」
ルシアがエイビーの口をふさいだ。
慎重に前進する。 こんなことならカービンを持ってきておくのだった。
談話室に誰もいないのを確認し、機関室のドアの前へ。
何の気配も無い。
しかし彼女の目にはドアの大型ノブが妙な光を放ったのに気付いた。
慎重に近寄って見てみる。
なにやら透明な粘液のような物がこびりついているらしかった。半分乾きかけている。
慎重に機関室の中をのぞく。
誰もいない。
彼女は一気に中に飛び込むと、ドアの裏側の壁をチェックした。
やはり誰もいない。
エイビーが小声で話しながら不安そうに入ってきた。
「なんですか?また密航者でも?」
ルシアは首を振って機関室内をチェックした。
エイビーもあたりを見回す。
パワープラントのコントロールパネルの脇には手すりがあり、吹き抜けになっている第3層のジャンプドライブ部へ落ちないようになっている。
その手すりにもさっきと同じ妙な粘液のような物がついていた。
彼女が視線を下に移すと、6メートルほど下のジャンプドライブ区画の床に、頭から血を流したシーガルが倒れているのが見えた。
二人の密航者はそれぞれ船室に閉じこめた。
マービンが見たところ、シーガルの死因は鈍器による頭部の骨折だった。これはジャンプドライブ区画に落ちたときのものかと思ったが、ドライブ区画にシーガルが頭をぶつけたような様子はなかった。
シーガルの遺体にも粘液は付着しており、これは採取して調べてみることになった。
とりあえず遺体は貯蔵室で冷凍して保存しておくしかない。
「ネバラー・・・」
ロビンがつぶやいた。
「それじゃ怪獣みたいですね。」
マービンが言ったが、誰も笑わなかった。事実怪獣かも知れないのだ。
今ローバンと雇われクルー4人がいるのはブリッジだった。
とりあえずネバラーに知能があった場合、ブリッジを占拠されるのだけは避けなければならない。
「アンチハイジャックプログラムを起動する。」
ロビンが重々しく宣言し、コンソールを操作した。
ホロディスプレイにメッセージが表示された。
「NO DATA」
「・・・・・・あの・・・ローバンさん」
「なにかね?」
「もしかしてアンチハイジャックプログラムを購入してないのでは?」
「なに?購入?最初から入っているものではないのかね?」
「・・・・・・」
こうしてプログラムの起動はあきらめられた。
アンチハイジャックプログラムが起動すれば、航海記録にその旨が記入され、あとで審査にかけられるがとにかく全室のモニターと全てのコントロールが行える。
つまり起動できなければ各部屋はプライバシーに守られているのだ。
「こっちから狩り出さないと仕方がないようですな。」
チークがカービンの弾倉をチェックしながら言った。
一応全室ロックはしたのでネバラーが移動することは無いはずだった。しかし現在どこにいるのかは分からない。
「ところでエイビーさんとビートさんは?」
マービンが気になっていたことを聞いた。
「彼らにはシーガルの遺体を貯蔵室に運んでもらっている。もちろんカービンは持たせたよ。」
「大丈夫かな・・・」
そこでコール音が鳴った。 通信士席に座っていたマービンが出る。
「ブリッジです。」
「こちらエイビーです。あの・・・夕食はなにがよろしいでしょうか?」
「は?」
「ばたばたしてしまって準備が遅れてしまいました。申し訳ありません。なにかリクエストがありましたらおっしゃってください。」
話がいきなり日常的すぎてどうしてよいのか分からない。マービンの頭の回りにクエスチョンマークが飛び交った。
「それはどうも・・・・で、ビートさんは?」
「はい。前菜は生ハムを使ったサラダとスープにしようということになりまして、ただいま材料をとりに行っております。」
「一人で?」
「はあ。本当はシーガルの役目なのですが・・・」
どうやらこういう状況に慣れていない付き人二人はすっかり混乱してしまっているようだった。
無理もないが、まさか一人で行動するとは予想もしなかった。
会話を聞いていたチークとルシアが即座にカービンを持って立ち上がった。
「貯蔵室だな!」
「待て!全員で行こう」
ビートは貯蔵室ですぐに見つかった。
シーガルと同じように頭を割られ、粘液に包まれて。
みんなが来たときにドアは閉まっており、誰も外に出た様子はなかった。
つまりネバラーはまだ貯蔵室内にいる確率が高かった。
しかしいくつもの冷蔵&冷凍パッケージと作りつけの棚が並んだ室内は、すぐ手前しか見通 せなかった。
銃を構えて奥へ行こうとするチークをロビンが止めた。
「なんで?」
ささやき声で会話する。
「ここで発砲するのはまずい。下手したら食料が駄目になって全員ジャンプアウトする頃には餓死しかねない。」
言われてみればその通りである。貯蔵室の冷蔵装置がいかれてしまったら食料のほとんどは駄 目になるだろう。
「しかしここにネバラーがいるのはほとんど間違いない。」
ロビンが研究所から借りてきたビデオカメラを引っ張り出し、貯蔵室の入り口あたりに固定した。
「ここにはカメラが無い。とりあえずこれでネバラーの正体を探ろう。ドアを外からロックすれば逃げられることは無いはずだ。」
全員とりあえず展望ラウンジに集まり、カメラが送ってくる画像をモニターしていた。 もちろん何かあってもすぐ対処できるように完全武装である。
チークとルシアは度数の高い酒を選んでそれも装備の一つとした。火炎瓶代わりである。
しばらく何の変化も無かった映像に、人影のようなものが一瞬映った。
食い入るように見つめていると、人影は次第にカメラに近づいてきた。
ぼさぼさ頭の男のようである。手に棒のような物を持っているようだが、貯蔵室の照明は暗く、はっきりとは分からなかった。
寒いだろうに元気そうである。
男はカメラの前に来ると、手に持った棒のような物を振りおろした。
画像が途切れ、砂嵐が表示された。
チークが立ち上がった。 すぐにルシアもロビンもマービンも立ち上がった。 ローバンとエイビーもついてゆく。
「どうするつもりかね?」
ロビンが小声で応えた。
「状況にもよりますが、敵意を示すようなら・・・・」
「処理だ!」
チークが叫んで走り出した。
みんなもあわてて走り出す。
どたどたと螺旋階段を下り、エレベーターに乗り換えて第3層へ。
貯蔵室のドアは中からぶったたかれているらしく、ドンドンという音が聞こえていた。
チークとルシアが素早くドアに近寄り、チークの手合図でルシアはドアの反対側に着いた。
他のメンバーは船倉側の通路から貯蔵室のドアに銃のねらいを付けている。
チークが慎重に開閉スイッチに手を伸ばし、操作した。
ノブが回転し、ドアが開く。
男はすぐには姿を現さなかった。
最初に右足が出てきた。
ぼろ布のような服を着ているようだった。
男が姿を現した。
ぼさぼさの頭に無精ひげだらけの顔、目はどこかにいっちゃっていた。
自分が銃口を向けられて囲まれているのに気付くと、右手に持った鉄パイプを振り上げ、ぼたぼたとよだれを垂らしながらだみ声でわめいた。
本当に怪獣の吠え声のようなわめき声はこう言っていた。
「ミナゴロシジャア〜〜〜〜〜!!!!」
チークのカービンを皮切りに、全員の銃が火を噴いた。 仁王立ちのまま蜂の巣になるネバラー。 チークは火炎瓶まで投げつけ、さらに連射した。
ごうごうと炎をあげながら、とうとう怪獣ネバラーは倒れ、動かなくなった。
宇宙船シナノマルの人々 第4回 終了
NEXT
リプレイホーム
化夢宇留仁の異常な愛情
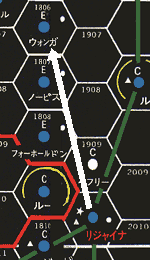 そんなこんなで貴族と3人の付き人と4人の操船担当者を乗せたY型ヨットは、なんとかウォンガへ向けてジャンプに入った。
そんなこんなで貴族と3人の付き人と4人の操船担当者を乗せたY型ヨットは、なんとかウォンガへ向けてジャンプに入った。
 女性は倒れたまま動かない。マービンが駆け寄ろうとするとチークが叫んだ。
女性は倒れたまま動かない。マービンが駆け寄ろうとするとチークが叫んだ。