犬神家の一族(2006)
市川崑監督
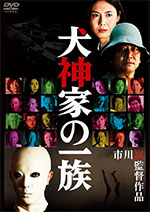 を観た。2006年のリメイクの方。
を観た。2006年のリメイクの方。
もう何度も書いているのであらすじは割愛する(笑)
原作を読んでからいつものパターンで映像化作品を観まくっていたのだが、最近のカール大公さんの日記で本作を見逃しているのに気付いた。
で、調べてみたらDVDをコピーしたのがちゃんとあった(汗)
なにしろ何度も映像化されているので見る準備まではしたものの、存在をすっかり忘れていたらしい(汗)
で、やっと観た感想だが、残念ながらこれまで観た同原作の映像化作品の中では最低の評価になった。
根本的なところを言えば、あの名作の監督が当時の主役(と一部のキャスト)を復活させてまでリメイクした作品なのだから、最初はアイデアだけはあったけどできなかった表現とか、技術的に発達した今だからこそできることとかを投入しているものと期待していたのだが、結果としてはどうしてリメイクしたのか意味がわからないという残念なことに(汗)
旧作のポイントとしてはなんといってもスタイリッシュな映像だが、本作ではそれがことごとく中途半端な画角のテレビドラマみたいな映像になっており、ものすごいパワーダウン感(汗)
そこでなんでもっと引かないの?とか、そこはもっとドアップでしょうというカットの連続だった(汗)
物語としてはまあまあ原作通りで、琴の先生は一応登場するが設定は削除とか、なぜか映画オリジナルの屋根の上の死体は再現とか、お約束の範疇でもあるのだが、なんだか異様にテンポが早くて情報をしっかり視聴者に伝える努力を放棄している感が。
もはや今更ストーリーを丁寧に説明する必要もないと思ったのかもしれないが、釈然としなかった。
深田恭子のお春はいい感じだったのだが、旧作の坂口良子のお目々キラキラが素晴らしすぎてまだまだ手が届くまでは行かない感じ。
目力という点では仲代達矢の遺影が強烈過ぎてすごかった(笑)
唯一旧作を超えているのはヒロインのエロさだと思う(笑)。
松嶋菜々子は特別美人でも可愛くもないが、顔のエロさは圧倒的で、映っているだけで変な妄想に浸ってしまう(笑)
しかしそういう最終兵器感のある彼女も、ある要素でドラマ的には違和感がありまくる。
それが背の高さで、172〜175cmくらいだと思うのだが、本作のあらゆるキャストの中でも目を引くほど高く、本作の設定時代である昭和22年では見世物になってもいいレベルなのでは(汗)
基本的なところでは豪華すぎる役者たちも演技の粗が目立ち、首を傾げることが多かった。
これは脚本の完成度からくるものかもしれない。特にラスト近くの息子を殺された母親たちの反応とか、正気の人間とは思えなかった(汗)
ちうわけで残念な結果になってしまった。
それにしても腑に落ちないのは、監督がリメイクで何をしたかったのか全くわからないというところに尽きる。
20250120(mixi日記より)
20250120
MM9 インベージョン
山本弘著/東京創元社
 を読んだ。OKさんに借りて。2016年6月4日。
を読んだ。OKさんに借りて。2016年6月4日。
クトウリュウとの伝説の戦いに勝利したヒメは、冬眠状態に移行。そのヒメを輸送中の自衛隊のヘリに隕石らしき物が衝突した。
一方もと気特対隊員の案野悠里の1人息子一騎は、頭の中に響く少女の呼び声に導かれ、自衛隊のヘリが墜落したと思われる湖に向かった。そこで彼は宇宙怪獣に襲われ・・・。
前作は連作短編の形式だったが、本作からはがっつり長編になった。
大筋では怪獣ヒメに「宇宙の正義を守る精神寄生型宇宙人」が憑依し、地球を侵略しようとする宇宙人と対決する(笑)という物語になっており、前作よりも更にウルトラマン度が上がっている。
しかししっかりした長編になったおかげで、パロディっぽいおちゃらけ感が薄れ、パンチのある本格ウルトラマン小説(笑)として楽しめるようになった。
と言ってもオマージュはそこら中にちりばめられており、と言うよりもこのシリーズがそもそもオマージュで出来ているのだが(笑)、そういう視点でも充分に楽しめるようになっている。
やはり最高に盛り上がるのは後半の宇宙怪獣対ヒメ(精神寄生型宇宙人憑依中)の対決で、流石にこの著者は王道を外さない。
自衛隊との連携は燃える♪
20160620(mixi日記より)
20250121
MM9 デストラクション
山本弘著/東京創元社
 を読んだ。2016年6月6日。OKさんに借りて。
を読んだ。2016年6月6日。OKさんに借りて。
一騎とその母の悠里、一騎の彼女の亜紀子、そして精神寄生体ジェミーが憑依したヒメは、東海村の小さな神社に閉じこめられることとなった。
彼らは宇宙からの侵略に対する重要な戦力でもあり、同時に敵につけねらわれる標的でもあったのだ。
しばらくは平穏な日々が続いたが、侵略の魔手は着実に彼らに迫っており、同時に異星の神である今までに無い強力な怪獣が地球に現れようとしていた・・・。
3部作完結編。今回も長編である。
もはや気特対は完全な脇役になってしまい、メインはヒメの神話的復活と、一騎少年のもやもや(笑)、それに異星の神との対決に絞られている。
もちろんオマージュも健在で、怪獣ならばなんでもいいのか「グエムル」まで世界の取り込んでいるのには笑ってしまった。
メインストーリーの方もオマージュを骨格部分にまで浸透させつつ、骨太の物語に昇華させており、大いに楽しめた。
しかし今回は神話との接点も大きく取り上げられているのが、人によっては好みが別れるかもしれない。
化夢宇留仁は面白かったが少々引っ張りすぎではないかとも思えた。
とりあえずこれで3部作が完結したわけだが、非常に高いレベルで熱い作品になっていると思う。特に2部と3部。
残念なのはやはり本作での気特対の脇役ぶりで、そこはなんとかもう少し活躍の場が欲しかったところである。
20160621(mixi日記より)
20250122
ローダンシリーズ35
アトランティス最後の日
松谷健二訳
 半空間に死はひそみて
半空間に死はひそみて
クルト・マール著
ようやくワンダラーを発見・・・するはずが、またしてもその姿が見えない。
しかし奇妙な次元の歪みのようなものが見つかった。どうやらワンダラーが異時間空間から脱出したときに問題が生じたらしい。
しかしグズグズしてはおれない。ローダンたちに残された時間は多くはないのだ。
この異時間関連の説明がどうも面白くない。
もっともらしいことを言っているが、全然意味がわからないし、それに付随した現象がどれもこれも都合がよすぎるというのもある。
この話ではブリーが薄い山を突き抜け、通常世界ではその影響で嵐が・・・とか、どう考えても納得できない。
単に縮んでいるだけで容積や質量は変化ないのに、なんで突き抜けられるのか?
突き抜けられるのならその抵抗は無いので嵐も起こらないのでは?
一瞬で山を突き抜けたら嵐くらいでは済まないし、ちうか伸びた方はなんでそんなに丈夫なんだ?
とか、ものすごくSFっぽいのに都合がよすぎてSFらしい面白さに繋がらないのだ。
まあこのシリーズにハードSF並の内容を求めるの方がおかしいのも確かなのだが(汗)
非常に珍しくブリーが独自の判断で活躍したのはよかった。
アトランティス最後の日
K・H・シェール著
なんとか細胞活性シャワーを浴びることができたが、ブリーが若返り始めた(汗)
どうも半空間に存在した状態で浴びたのがまずかったらしい。
その後色々と苦労してブリーは元に戻るのだが、それからアトランが過去の記憶を語ることに・・・。
アトランの体験したアトランティスの最期にまつわる物語が、大規模かつ悲壮で滅茶苦茶盛り上がった。
まさかアトランティスが沈んだ原因がそんなにストレートなものだったとは(汗)
ちうかアトランの部下たち、特に艦長タルツがかっこよすぎる。
タルツ〜〜〜〜〜(泣)
やっぱりこのシリーズは、こういうドラマ的なところやストーリーが楽しみどころだと思った。
20250123(mixi日記より)
20250123
トワイライト・テールズ
山本弘著/角川書店
 を読んだ。2016年6月8日。OKさんに借りて。
を読んだ。2016年6月8日。OKさんに借りて。
MM9の世界を舞台にした短編集。MM9の世界と言っても「怪獣」のいる世界という条件しかないわけで、時代も場所もまちまちである。
生と死のはざまで
倒壊したショッピングセンターの地下に閉じこめられた少年と女性自衛官。
彼らの頭上には傷ついた怪獣が居座っており、逃げ出すことも出来ず、そしていつ崩れるかも分からない。
その少年は現実世界からファンタジーの世界の空想に逃避していた。そんな彼が現実と向き合わざるを得ない状況に対し・・・。
なんとも言えない作品。ありきたりなような、斬新なような。
特別面白くはない。
夏と少女と怪獣と
モンタナ州北西部にあるフラットヘッド湖には、怪獣が棲んでいると言われていたが、目撃者は少なかった。
少年ハロルドの祖父はその1人だったが、怪獣が存在するという確かな証拠は残さなかった。
ハロルドは祖父の遺した怪獣の鳴き声のテープを利用し、怪獣を呼び寄せようとしていた。
そんな彼が美しい少女タリーと出会い、恋に落ちるが、その後2人は恐ろしい事件に巻き込まれることに・・・。
なんとなくスティーブン・キングを思わせる雰囲気のいい作品。
変にロリコン趣味とかの描写が生々しいところはこの著者っぽい(笑)
怪獣神様
タイの田舎の湖に現れたMM9級の大怪獣は、異星の神様だった。
神様と心を通じ合った少女シリヤムは、普段から彼女を酷い目にあわせている村の人々への復讐を神様に願うが、神様はそのような争いの結果を知っており、断る。
その神様に、人間達の軍隊が攻撃を仕掛け・・・。
なかなか味わい深い作品。なんとなく「大魔神」風(笑)
ある意味宗教の本質を逆説的に解いた内容でもある。
怪獣無法地帯
1968年3月。アフリカ大陸コンゴ共和国。
怪獣だらけのジャングルの中を進む2人の男と1人の女性。
彼らはある任務を負ってこのジャングルに潜入していたのだが、強大な怪獣に追い回されて任務どころでは無くなりかけていた。
そんな彼らを救ったのは、巨大なゴリラ型怪獣を操る若い女性だった・・・。
前半はターザン&キングコング。後半はSFホラーっぽい展開。
なんだか出てくるメインの怪獣のサイズが小さいせいか、タイトルで想像するイメージとは大きく異なる印象。
正直後半はあまり面白くなかった。
可能性に充ち満ちているMM9世界だが、この短編集はそれを生かし切れているとは言えない内容だったように思う。
退屈することはないにしろ、もっともっと面白い物語ができる世界だと思うので、今後の展開に期待したい。
と言うか、ラブクラフトのクトゥルフ神話世界みたいに誰でも参加できる創作世界に成長したらいいのにな。
20160622(mixi日記より)
20250124
吸血鬼愛好会へようこそ
赤川次郎著
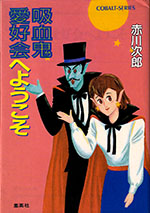 吸血鬼愛好会へようこそ
吸血鬼愛好会へようこそ
夜道で女性が通るのを待っていた若い男は、女に襲いかかろうとしたが逆にノックアウトされてしまう。
その男小田切弘は吸血鬼愛好会に入るために女性を気絶させなければならなかったのだが、失敗した上にコートを置き忘れ、しかもその日そのすぐ近くで若い女性が喉を切り裂かれて殺されていた・・・。
いろいろとおかしなところの多い話で、なぜそれが語られ、逆になぜぞれは語られなかったのかの理由がわからない部分が多い。
上に書いた冒頭の「女性を気絶させなくてはならない」というのもそのひとつ(笑)
まあそれでも展開的には盛り上が・・・らなくもない(汗)こともない(汗)・・・感じで、全然面白くないということはなかった(笑)
吸血鬼は鏡のごとく
新人アイドルの沢田今日子は今日も忙しい日々を送っていたが、楽屋の鏡にアイドルらしい少女がナイフで刺されて殺される映像が映し出されるのを見て気を失ってしまう。
話を聞いたマネージャーの幸枝は、その少女がかつて彼女が初めてマネージャーについた宮川サト子という新人アイドルだと気づく。
しかしその後今日子が危なく大きなセットの下敷きになりそうになり・・・。
鏡に写った過去の映像(トリックなし)が発端というのは普通のミステリーでは許されないが、本シリーズでは全然許容範囲(笑)
むしろこの話は最後まで誰が犯人なのかをうまく引っ張り、序盤に出てきた何気ない情報が生きてきたりと、このシリーズにしては(笑)ミステリーとしてなかなか楽しめた。
ただ犯人の過去の殺人の方の動機の説明がおざなりすぎると思った(笑)
吸血鬼に向かって走れ
駅伝のアンカーに選ばれたエリカは、吸血鬼の能力を発揮して速く走りすぎてもいけないので困っていたが、別な選手があまりにも人間離れした追い上げをしたのに疑問を持つ。
結局エリカは3位だったが、トップの2人の少女はなにかわけありらしかった・・・。
この話も最初の話に輪をかけておかしなところが多く、オチもなんだかヒッチャカメッチャカだった(汗)
流石にその犯人と動機と能力は無いわ(汗)
あの人もそこで咄嗟にそんなこと思いついてそんなことをさせるとか、ありえないわ(笑)
時間がなくてオチも考えずに適当に書いていたら、結局最後近くまで落ちが思いつかずに無理やりなんとかしたという感じ(笑)
ちうわけでなかなか酷かった(笑)
このシリーズは基本は低空飛行なのにその中でも出来不出来の差が激しいのだが、本作はその低い方で安定していた感じ(汗)
ちうかクロロックが調査のために催眠術を使うのはまあいいとして、犯人側がばんばん使うのは無しだと思うぞ(笑)
20250125(mixi日記より)
20250126
剣客商売十一 勝負
池波正太郎著
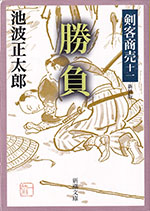 剣の師弟
剣の師弟
道に迷って木立の中に入ってしまった小兵衛は、侍3人が町人1人を取り囲んでいるところに遭遇するが、意外なことに町人が侍3人を圧倒しているようだった。
その後煮売り酒場に落ち着いた小兵衛だったが、そこにさっきの町人が訪れる。しかもその連れの侍はかつての小兵衛の弟子だった・・・。
色々と切ない話で、それは当時の江戸の状況も大きく影響している。
それがなんだか今の日本の更に悲惨な状況を思い起こさせて泣きそうになった(汗)
勝負
試合をすることになった大治郎がそれを小兵衛に告げると、「負けてやれ」と言われて困惑する。
相手は28歳の一刀流の使い手で、大治郎に勝てば八万石の城主の剣術指南役に召し抱えられるのだ。
しかし勝負をわざと負けるなどという選択肢は思いつきもしないクソ真面目な大治郎はモヤモヤしまくり・・・。
一歩大人になる大治郎(笑)
そして子どもも生まれる(笑)
初孫命名
大治郎は息子の名前を小太郎にしたいと言うが、小兵衛が却下。
その後籠に乗っていた小兵衛だが、腹を壊して林の中へ(笑)
そうしてや林の中でしゃがんでいる小兵衛の耳に聞こえてきたのは、なんと小兵衛の隠宅への襲撃計画だった・・・。
最後の一行が小兵衛の親友の松崎助右衛門の台詞なのだが、これが最高の切れ味のオチになっていて痛快♪
その日の三冬
産後20日ほどで初めて外出した三冬は、寺の境内で浪人風の男が侍を斬り殺す現場に出くわすことに。
しかもその浪人は三冬のよく知る人物だった・・・。
三冬の優しさがいい感じなのだがこれまたなかなか切ない話で、なんとなく「アダルト・ウルフガイ 狼は泣かず」を思い出した(汗)
時雨蕎麦
小兵衛に声をかけてきたのは、おはるが「鰻の頭」と呼んでいるひょろ長い肢体の川上角五郎だった。
その角五郎は60歳にもなろうというのに40にもならない若い女との結婚が決まったと浮き立っていた。
その後結婚相手がいる店に行って話を聞いた小兵衛はそれが大きな勘違いだと知り・・・。
63のお崎さんがかっこよくて可愛い(笑)
助太刀
大治郎は柳原土手でカタツムリの絵の描いてある団扇を購入したむさ苦しい男のやっている露店を1年ぶりに見つけ、嬉しくなった。
今度は小兵衛の分も含めて大金を払って購入するが、その後団扇屋がガラの悪い侍3人に殴られているのを見かけ・・・。
上の紹介文では全然本編に入っていない(笑)
要するに敵討ちの話なのだが、敵討ちシステムというのはやはりどうも条件が厳しすぎる気がする(汗)
また敵討ちと同時に再び小兵衛の隠宅襲撃が発生するのだが、今回は大治郎までおり、10人がかりでも話にならないのだった(笑)
小兵衛が世話した結果がどうなったのかを知りたい(汗)
小判二十両
橋場の船宿「鯉屋」でおはるの舟を待っていた小兵衛は、そこにキツネのような顔の町人と浪人体の五十男が訪れるのを見る。
浪人風の男はまたしても小兵衛のかつての弟子だった・・・。
その男小野田万蔵の生い立ちからその後の人生どこもかしこも切なすぎ、あとで説明を聞くと小兵衛がうるうるしていたのも納得(汗)
ところでこの話で小兵衛の夏の好物として紹介されていたのが、井戸水でよく冷やした豆腐にすりおろした生姜をのせて醤油と酒と数滴のごま油を混ぜたかけ汁で食べるというもので、そりゃあうまいわ(笑)
孫もできて、なんだか小兵衛がだんだん爺くさくなってきた。まあ元々爺なのだが(笑)
おそらく著者の年齢とか考え方とかも大きく影響しているのだろうと思う。
20250131(mixi日記より)
20250201
ウルトラマンデュアル
三島浩司著/早川書房
 を読んだ。2016年6月12日。OK氏に借りて。
を読んだ。2016年6月12日。OK氏に借りて。
我々の地球とは少し違う歴史を歩んだ地球。
そこではヴェンダリスタ星人の侵略によって、人類は奴隷の一歩手前まで追いつめられていた。
人類が奴隷化されるのをギリギリで救ったのは、光の国の活躍によるものだった。
しかしヴェンダリスタ星人も光の国も、その戦いで多大な損害を受け、本国からの援軍が来なければ動きようのない状況だった。
しかも残った戦力はヴェンダリスタ星人が圧倒しており、人類は光の国の生き残りを守るために国土の一部を光の国に占領されたということにし、なんとかその居場所を作った。
ヴェンダリスタ星人は次々にそこに怪獣を送り込んだが、それに立ち向かったのは「ウルトラ・オペレーション」を受けてウルトラマンとなった人類だった・・・。
要するにウルトラマンの設定の一部を利用したSF小説である。
しかし結論から言えば、結果はウルトラマン小説としても、SF小説としても非常に中途半端だと言わざるを得ない。
そもそもこの物語を「ウルトラマン」として描く必要はどこにあるのか?
化夢宇留仁の感じたところでは、「ウルトラマン」が好きな人がこの本を手に取る可能性を高めるということ以外には見いだせなかった。
先日読んだMM9シリーズは、「怪獣」が存在する世界という設定を掘り下げ、他にはない面白さや特徴を作り上げ、SF小説としても怪獣小説としてもパロディ小説としても楽しめるように出来ていた。
ところが本作では素材として使用された「ウルトラマン」という要素が傷つけられているばかりで、発展的にオリジナル作品として昇華されたと思えるところが何一つ無い。
SF小説として見ればどうかと言えば、これまた全く見事なまでに見るべきところがない。
レジスタンス小説(?)として見れば少しは面白いところもあったか???
とりあえず化夢宇留仁的には残念な作品だった。
201606221(mixi日記より)
20250202
レジまでの推理 本屋さんの名探偵
似鳥鶏著/光文社
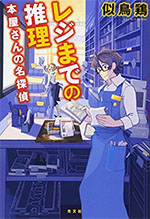 を読んだ。2016年5月28日。OKさんに借りて。
を読んだ。2016年5月28日。OKさんに借りて。
本屋さんを舞台にした連作ミステリー。最近こういうの流行ってるみたいね。
7冊で海を越えられる
ジャンルも雰囲気もバラバラの7冊の本を彼女から送られた男性が、その理由が分からず、もいつめた挙げ句にその本を送った本屋に相談してきた。
彼は来月には彼女を置いてアメリカに発たなければならなかった。彼女からのプレゼントには、会えなくなる彼に対してのメッセージが隠されているのではないかと言うのだが・・・。
破綻があるわけではないが、少々強引すぎる印象を受けた。
いくらなんでもお金の無駄遣いではないか(笑)?
全てはエアコンのために
友人でもある作家のサイン本が盗まれたという男が訪ねてきた。
彼の本を盗んだのは、なんとこの本屋の店員だと言う。
状況から彼が盗んだのは間違いないのだが、しかし問いつめようにもどうやって盗んだのかが分からない・・・。
このトリックは最初の話以上に強引だと思った。
いくら「可能」でも、実際にやるのはあまりにも非現実的だと思う。
通常業務探偵団
人気若手作家のサイン会を開くことになる。
サイン会自体は盛況で大成功に終わったが、その翌日、店に貼ってあったサイン入りのポスターに酷い落書きが発見され・・・。
この作品のトリックは「リアル」ではないにしろ、強引とまでは思わなかった。
まあ犯人が○○○○○という設定であれば、なにをやってもおかしくないし(笑)
本屋さんよ永遠に
開き直る万引き犯、雑誌に挟まれた脅迫文の書かれた紙、その本屋には滅びの時が迫っているように見えた。
そして燃え上がる炎の中に立っていたのは・・・。
メタトリックを取り込み、誤認識に誘導。犯人は意外な人物かと思わせ、実は人違い(笑)
これまでの展開をふまえた上での少々凝ったトリックで、本来ミステリーが解こうとする謎とは違うところに謎を配置しているのは興味深かったが、ストライクというわけにはいかなかった。
化夢宇留仁も本屋でアルバイトをしていた経験があるからか、そこまで深くのめり込める商売とは思えないのだ。
料理は別としても、小売でこういう展開は考えにくいような。
というわけで文句ばかり書いてしまったが、決して面白くないわけではない。
むしろ読んでいる間はしっかり楽しめた。
ただ振り返ってみると少々アラ(?)が目立つように感じただけである。
キャラクターが弱いのが原因か???
201606223(mixi日記より)
20250203
多々良島ふたたび ウルトラ怪獣アンソロジー01
早川書房
 を読んだ。2015年10月23日。OKさんに借りて。
を読んだ。2015年10月23日。OKさんに借りて。
多々良島ふたたび 山本弘
怪獣の出現によって3名が死亡した多々良島の事件は2年半前のこと。
ようやく多々良島に2度目の調査船が派遣された。
しかしその船には新聞社の記者である若い女性がが密航していた・・・。
テレビのエピソードのダイレクトな続編になっており、同時にテレビでは謎だった多々良島にどうして怪獣が大量に生息していたのかの解答にもなっている。
まさに王道という感じで嬉しい。
ただし王道だけあって意外な展開という感じではないが、安心して楽しめた。
宇宙からの贈りものたち 北野勇作
夢うつつの中で体験するおかしなウルトラQ世界。
なにがなにやらさっぱり分からないが(汗)、なぜかウルトラQの白黒画面で展開される様が想像できるので、少なくとも雰囲気的には成功しているのだろう。
しかしやっぱりなにがなんだか分からない(笑)
マウンテンピーナッツ 小林泰三
女子高生久野千草はギンガライトスパークを使い、初代ウルトラマンに変身できる。
今日も怪獣デットンを倒すためにウルトラマンに変身したが、なんと民間の戦闘機に攻撃される羽目に。
戦闘機を操っているのは、世論を味方につけて強大な力を手に入れた自然保護団体マウンテンピーナッツだった・・・。
ギャグかと思いきや、黒い描写も多く、シチュエーションもえげつない。
なかなか悲惨な話で面白いが、ギンガライトスパークなど、最近のウルトラマンシリーズを観ていないと分からない要素も含められていて、最近のウルトラマンと言えばメビウスしか知らない化夢宇留仁にはついていけない部分も多かった。
しかし変わり種でなかなか面白い。
影が来る 三津田信三
カメラマン江戸川由利子は、自分がもう1人いることに気付く。
自分とは僅かに時間をずらし、あたかも自分と同一人物であるかのように振る舞っている何物かがいるのだ。
そしてそれは誰かのいたずらなどではなく、奇怪な現象が実際に起こっていると判明し・・・。
ウルトラQの1エピソードという体裁。内容的にはSFというよりもオカルト寄りだが雰囲気はバッチリで、本当にウルトラQの新しいエピソードを観たというお得な気分が味わえた。
こういうストレートなのもいいね。
変身障害 藤崎伸吾
かつてウルトラセブンとして幾多の戦いをくぐり抜けてきたモロボシ・ダンは、なぜかウルトラセブンに変身できなくなって悩んでいた。
悩んだ末に訪れた精神科の医院で彼を診断した精神科医は、なんと彼と同じ症状に苦しんでいる患者が他にもいると言う。
後日グループセラピーのためにダン以外に集まったのは、昔ウルトラセブンが倒したはずの宇宙人・・・に変身できないと悩んでいる人々だった・・・。
非常に面白い。
ミステリアスな展開に、コメディ要素も取り入れ、SFとしても成立している。
またこの本は作品毎に異なる挿絵がついているのだが、この作品は挿絵も最高の出来。
文句なしの名作。
怪獣ルクスビグラの足型を取った男 田中啓文
怪獣の足型を取る職業の男達の熱い戦い。伝説の怪獣ルクスビグラは実在するのか?
昔の子ども向け怪獣図鑑には必ずと言っていいほど怪獣の足型が掲載されていた。あれを最初に思いついた人は誰なのだろう?素晴らしいアイデアだと思う。
そして怪獣が実在する世界では、当然その足型を取る人々も実在することに(笑)
この辺の思考の発展は実に面白い。
面白いが作品としてはもう一つに感じた。
もっとストレートに足型を取る職業を描ききってほしかった。
痕の祀り 酉島伝法
「怪獣のようなもの」と、「ウルトラマンのようなもの」が実在する世界。
その世界ではそれらを元に「ウルトラマン」というテレビ番組が作られ、人気を博している・・・。
物語は「怪獣のようなもの」の死骸を解体して処理するチームの視点で進む。
SFっぽい雰囲気なのだが、なんだか観念的でよく分からない(汗)
とりあえずイラストは加藤直之大先生で素晴らしいのだが、だからこそ逆に残念(汗)
というわけで色々な作品を楽しめた。
それぞれに異なる挿絵がつけてあるのが素晴らしく、これぞアンソロジー!という感じである。
面白いのもそうじゃないのもあるが、次はどんな作品なのかワクワクできるのがアンソロジーの一番の魅力ではなかろうか。
20160625(mixi日記より)
20250204
フューリー
デヴィッド・エアー監督
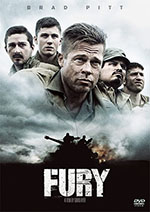 去る12月8日に視聴。
去る12月8日に視聴。
シャーマンイージーエイトとその戦車長、新米戦車兵などが主役の戦記物。
なかなか面白かった。
やはり一番の盛り上がりはティーガー1とのガチ対決シーン。
ちょっと対戦距離が近すぎてリアリティという点ではどうかという気がしないでもなかったが、どっちも実車がガリガリ動いてアクションされたらそら盛り上がる。
残念だったところは主に2点で、1つは画面にやたらに青いフィルターがかかっていたこと。
この映画でイージーエイトを知った人はシャーマンは青い戦車だと思いこむに違いない(汗)
もう1つは最後の戦車籠城戦。流石にシチュエーションに無理がありすぎるし、ドイツ軍が不甲斐なさすぎる。
しかし全体的には戦場の雰囲気をいい感じに伝えていていい映画だったと思う。
そしてこの映画を一言で言えば・・・・戦車版松本零士「大艇再び還らず」である(笑)
そのまんまのシチュエーションもある(笑)
20201218(mixi日記より)
20250205
キリンモワールへの道
〜幾人かの旧友との再会に至るメルニボネのエルリックの顛末〜
マイクル・ムアコック著/健部伸明訳/ナイトランド・クォータリー vol.34
 を読んだ。
を読んだ。
「下なる世界」をさまようエルリックとムーングラムの前にオルランド・フュンクと名乗るマルチバースを行き来する男が現れる。ところがそこに堕落しきってほとんど人間らしさをも失っているアマーキア騎士団が襲撃する。
それらを撃退し、騎士団の宿営地らしきところにたどり着くと、そこにはエルリックと同じ白子のメルニボネ人らしき女性が囚われていた・・・。
最初からエルリックとムーングラムのおしゃべりがやけに長々と続き、なんとなくこれまでと雰囲気が違う。
またその会話や文章になんだかよくわからない単語が山のように出てくるも、なにしろわけがわからないのでクエスチョンマークが大量発生(汗)
謎のメルニボネ人女帝メラレはメルニボネ人の歴史の新たな要素となるも、やっぱりわけがわからず(汗)
そしてそこに新たな襲撃が・・・というところで終わり(汗)
なんでも長編の最初の部分らしいのだが、いくらなんでもぶつ切りすぎ(汗)
更にそのあとにくっついている訳者の解説によると、ムアコックは既出の作品の内容もコロコロ変更しているらしく、中にはエルリックと同行していた者をムーングラムからスミオーガンに変更したりとか、話の順番を入れ替えたりとか、なかなか好き放題やっているらしい。
そもそも多元宇宙が絡んでややこしいのに1つの世界の中でもそんな適当に内容を変えていかれては多元宇宙の多層構造というほんとにわけのわからないことになる・・・ちうかなってる(汗)ので、どうにかしてほしい(汗)
それにしてもアコックはまだまだ現役でエルリックを描き続けているのがちょっと恐ろしい(汗)
20250206(mixi日記より)
20250206
メンフィス・ベル
マイケル・ケイトン=ジョーンズ監督
 去る12月13日に視聴。
去る12月13日に視聴。
史実を基に第二次世界大戦時のイギリス在中の米空軍爆撃機隊の活躍(?)を描く。
若々しい搭乗員たち10名が変にひねることなく描かれ、後半の爆撃行でもただただストレートにその行程を描き出しており、非常に好感の持てる作り。
もちろん見どころは実機を使ったB17の描写で、発進シーンは鳥肌モノだし機内の描写も見飽きない情報量。
一家に1枚はDVDを常備すべき作品だった。
20201219(mixi日記より)
20250207
空軍大戦略
ガイ・ハミルトン監督
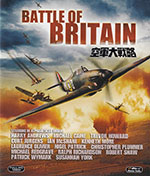 ずいぶん前になるが、去る9月19日には映画「空軍大戦略」を観た。
ずいぶん前になるが、去る9月19日には映画「空軍大戦略」を観た。
いわゆるバトル・オブ・ブリテンを描き出した群像劇で、英軍からの大局的なものと現場的な視点を取り混ぜて展開する。
歴史的にはドイツ軍が諦めた形で終局したわけだが、後の考証からすればロンドン空襲に固執せずに消耗戦に持ち込んでおればドイツの勝利は硬かったと思われる。
そういう部分もちゃんと表現されていて、興味深かった。
お楽しみの空戦シーンはストゥーカはラジコンだが実機も山程登場して盛り上げてくれる。
残念なのはBF109がスペインでライセンス生産されたHA-1109 / HA-1112を使用しており、エアインテークがごつくてかっこ悪いところで、この映画を見てあのスマートなBf109があんな形状だと誤解されるのは切ないところ。
他の見どころは・・・かっこいい貴族がぴったりの若きマイケル・ケインかしら(笑)?
20201219(mixi日記より)
20250208
BACK 記録&感想トップ NEXT
HOME
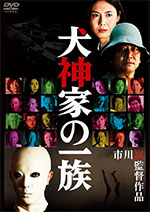 を観た。2006年のリメイクの方。
を観た。2006年のリメイクの方。 を読んだ。OKさんに借りて。2016年6月4日。
を読んだ。OKさんに借りて。2016年6月4日。
 を読んだ。2016年6月6日。OKさんに借りて。
を読んだ。2016年6月6日。OKさんに借りて。 半空間に死はひそみて
半空間に死はひそみて  を読んだ。2016年6月8日。OKさんに借りて。
を読んだ。2016年6月8日。OKさんに借りて。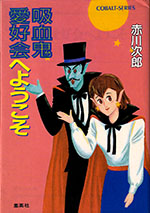 吸血鬼愛好会へようこそ
吸血鬼愛好会へようこそ 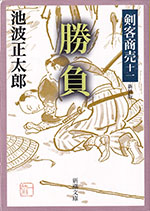 剣の師弟
剣の師弟  を読んだ。2016年6月12日。OK氏に借りて。
を読んだ。2016年6月12日。OK氏に借りて。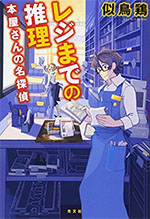 を読んだ。2016年5月28日。OKさんに借りて。
を読んだ。2016年5月28日。OKさんに借りて。
 を読んだ。2015年10月23日。OKさんに借りて。
を読んだ。2015年10月23日。OKさんに借りて。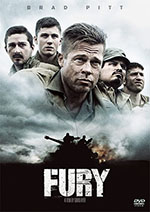 去る12月8日に視聴。
去る12月8日に視聴。 を読んだ。
を読んだ。 去る12月13日に視聴。
去る12月13日に視聴。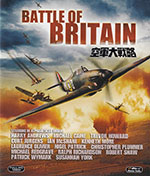 ずいぶん前になるが、去る9月19日には映画「空軍大戦略」を観た。
ずいぶん前になるが、去る9月19日には映画「空軍大戦略」を観た。