ルーンの杖秘録1 額の宝石之巻
マイケル・ムアコック著/深町真理子訳
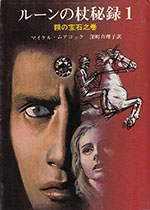 文明が崩壊し、剣と魔法が支配するようになった今から1000年ほど未来の地球。
文明が崩壊し、剣と魔法が支配するようになった今から1000年ほど未来の地球。
ヨーロッパはグランブレタンという狂気の帝国の支配下に落ちようとしていた。
その魔の手がまだ及ばぬカマルグ国では、伝説の英雄ブラス伯爵が防備を固め、帝国の手出しを防いでいた。
しかし祭りが大いに盛り上がって意気揚々と戻ってきた伯爵を待ち構えていたのは、グランブレタンのメリアタス男爵だった・・・。
というのが第1部の前半部だが、主人公ドリアン・ホークムーンは第1部には登場しないのだ(笑)
第2部で登場したケルン公爵ホークムーンはグランブレタンに国を占領され、慰みものにされるためにグランブレタンの本拠地であるロンドラ(旧ロンドン)に輸送されるが、メリアタス男爵はブラス伯爵への復讐にホークムーンを利用することを思いつき、彼の額に魔法の宝石を埋め込む。
そんなこんなでメリアタスの言いなりにブラス城へ向かうホークムーンだが・・・。
というわけでホークムーンの大冒険が始まるわけだが、エルリックと比べると非常に真っ当なファンタジー冒険譚という感じで、なによりホークムーンが普通にいい人(笑)なのと、変な剣を持っているわけでもないので仲間を殺したりもしないのだ(笑)
だからといって凡庸でつまらないということは全然無く、密度の高い物語で最初から最後まで十分に楽しく読めた。
やはり新鮮だったのは未来の地球が舞台ということで、地名なんかも微妙に現在からも想像できるような塩梅で、長距離の移動もそれが効いて風情がある。
またのちに別作品の主人公にもなる(らしい)ブラス伯爵もなかなか魅力的で、先のシリーズを読むのも楽しみにできた。
魔法使いと山巨人のハーフである相棒オラダーンもいい感じ♪
20250904(mixi日記より)
20250904
ウルトラマン 第3~4話


まさにウルトラマンのステロタイプと言える内容で、ウルトラマンとはこういう内容だということを1話だけ見せて説明するならこのエピソードを選ぶことになると思う。
見せ場も多く、やはり透明怪獣ネロンガの姿は見せないが質量は見せる演出や、怪光線を発射するときの2つの角が前に回転して鼻の角の光が先端に移動するなど、非常に凝ったディテール描写も素晴らしい。
後半の火力発電所での対決シーンは、そもそも施設が超大規模なのを活かしており、巨大な専用車両なども登場し、いつものようにTVシリーズとは信じられないような大規模なセットを破壊しまくっていてまさに見どころ満載。
化夢宇留仁的に気になったところは、いつもよりもメイクを頑張っているようで美しいフジ隊員(笑)や、火力発電所を守る自衛隊車両の戦車が車体はシャーマンだが長砲身の砲塔は小さくて見慣れない車種だったところ(誰か車種が分かる人教えてください/笑)。




第4話 大爆発五秒前
 
飯島敏宏監督
木星開発用に6個の原子爆弾を搭載したロケットML-1が事故によって太平洋に墜落。
積まれていた6個の原子爆弾のうち1個は日本海溝の深度5千mで爆発し、南洋の島々は津波に飲み込まれた。
残りの4個は回収されたものの、最後の1個は見つからないままだった。
洋上で原爆を捜索していた海上保安庁の巡視船に怪しい白い航跡が接近したかと思うと、巨大なラゴンが現れる。ラゴンの腕には最後の1つの原爆が・・・。
|


ウルトラQに出てきたラゴンが再登場。
化夢宇留仁はスーツの使い回しの別物だと思っていたのだが、なんとウルトラQのラゴンと少なくとも同一種族で、音楽が好きという特徴まで活かしている完全な続編だった(汗)
巨大化したのは原爆の放射能のせいである(笑)
しかしもっと根本的に違うところがあり、それはスーツアクターで、なにしろ元のラゴンの中にはウルトラマンの中の人が入っていたので、対決する都合上そういうわけにはいかず、今回のラゴンはオリジナルと比べるとずんぐりした体型で、アクションも無駄な動きが多くて少し残念だった。
例によっての化夢宇留仁の気になるポイントは、休暇をもらって旅行に行くというフジ隊員が連れがいるというので色めき立つ科特隊員たちだが、その連れはホシノくんで、しかもホテルでもなぜか科特隊のブレザー姿で色気のないことおびただしい(汗)
やはり子供向け作品ということで、そのへんのリアリティーに踏み込むわけにはいかなかったか(笑)
またキャップの指令で千葉に調査に行っていたハヤタが「白い航跡」が湘南に現れたということで急いで向かうのだが、最速の移動手段がフェリーというのが味がありすぎる(笑)
そして途中で出てきたスパゲティがあまりに不味そうすぎるのにはびびった(汗)
やはりこれも時代か(笑)
最後、起爆スイッチの入ってしまった原爆を持って飛び立ったウルトラマン。
爆発の閃光が見えてウルトラマンを心配するアラシやホシノの前に現れるハヤタ・・・って、助かったのはいいけど戻ってくるのが早すぎる(笑)
ウルトラテレポートを使用したか?しかしエネルギーはほぼ尽きていたはずだが・・・(汗)


20250906(mixi日記より)
20250907
聖者の行進
アイザック・アシモフ著/池央耿訳
 男盛り
男盛り
まだ生きていたのかと驚かれるアシモフがそのことについて書いた詩。
この詩を書いた当時(1966年)はアシモフはまだ46歳だったが、そのあまりの多作ぶりにとうの昔に亡くなった昔の作家だと思われていたらしい(笑)
女の直感
極秘に地球上で活動していたロボットが事故によって失われた。
それは今までUSロボット・アンド・機械人間社が開発したロボットの中でも最も進んだ思考能力を持っており、人間には不可能な量の情報を突き合わせて直感を働かせることができ、その能力で人類が目指すべき居住可能な惑星の選定を行っていたのだ。
そしてロボットを開発したマダリアンの最後の報告では、それが成功していたはずなのに、研究者たちはその様子を誰見ておらず・・・。
ロボットジェーンシリーズのボディを女性型にするという件があるが、そもそもこのロボットに人間のようなボディが必要な理由がよくわからない。
それと冒頭の事故内容があまりにも奇跡的な出来事で、神の審判かとさえ言いつつそのままなのが気になった。
スーザン博士が活躍するのは相変わらず楽しい。
ウォータークラップ
月世界から地球の深海居住施設オーシャン・ディープにやってきたデマレストは、ある決意を秘めていた。
人類のためには月と宇宙の開発を進めるべきで、深海などに予算を割くのは無駄以上の深刻な問題につながるのだ・・・。
蒸気を利用した深海のエアロックの描写が面白い。
それにしてもそもそもオーシャン・ディープはなんのためにあったのだ(笑)?
心にかけられたる者
前に読んだ「究極のSF -13の解答-」収録のものと同内容。
あっちの感想で化夢宇留仁は「そもそもロボットは人間をどうやって人間だと見分けていたのか???」という感想を書いたのだが、本書の冒頭のいつものアシモフのつぶやきで、そもそもこの作品は同じ疑問が出発点だったと知って驚いた。
ところがこれが同じ文章なのに意味は違うのだ。
化夢宇留仁が知りたかったのはもっと単純に、人間とそれ以外をどうやって見分けているかで、例えば寝たきりの人、部位の欠損のある人、子どもなど、ロボットはどこまでを人間とみなすのか、その線引きはどこなのかという疑問だった。
しかし最近のAIの様子や、更には本書収録の「バイセンテニアル・マン」でだいたいわかった。
なんとなくの見た目で判断しているらしい(笑)
天国の異邦人
その時代には同じ両親から2人以上の子どもが生まれるなどということは滅多に無かった。
また名前は名字も含めて本人が自由に名乗っていた。
そんな世界で同じ両親から生まれた顔もそっくりの兄弟が同じ目的を持って働くことになる。
それは水星にロボットを送り込んで調査を行うことだったが・・・。
最後なんだか爽やかな感じで終わるのはいいのだが、この話は納得のいかないところばかりでよくわからなかった。
真の名前はそれぞれにユニークな数字と記号が割り当てられているので名前はどう名乗ってもよいのなら、なんでそもそも名字が必要なのか?
兄弟の拒否反応もよくわからない上に、物語になにか影響しているとも思えなかった。
繊細すぎるロボットの反応を制御するために専用の超高性能コンピュータを地球に設置してコントロールするが、その通信には7分のタイムラグがあるというのはどう説明されても突っ込みどころしか無い。
またこの作品のロボットこそ人間型である必要性が(オチ以外では)見当たらない。
ゴツいタイヤ移動でいいじゃん。
というわけでこの作品は2人の編集者がそうしたように、ボツがふさわしいと化夢宇留仁も思う(笑)
マルチバックの生涯とその時代
超大型コンピューター「マルチバック」にコントロールされた世界。
パクストは端末を破壊しようとしたハインズを告発したことで、反コンピューターの組織から糾弾されることになったが、彼の計画上それは必要なことだった・・・。
オチは予測できるが、最後に付け加えられたという質問はなかなか深みがあってよかった。
またこの世界は「鋼鉄都市」の世界に近い雰囲気があるように思ったが、ほんとうにつながっているのかどうかはあっちを読み直してみなければ・・・(汗)
篩い分け
地球の人口は60億に達し、絶望的に食料が不足していた。
そんな中細胞膜の浸透力をコントロールして変化させることを可能にした研究を発表したロッドマン博士は、政府によって囚われの身となり・・・。
その話の流れで食べるとは思えない(笑)
バイセンテニアル・マン
マーチン家のロボット、アンドリュウにリトル・ミスが木彫りのペンダントを作るように命令すると、アンドリュウはあっという間に見事な作品を作り上げた。
彼は世にも珍しい創造力のあるロボットだったのだ・・・。
超名作。映画「アンドリューNDR114」の原作でもある。
化夢宇留仁が特に好きなのは前半部分で、その幸せな時間の流れに感動する。
聖者の行進
精神に異常のある人に対し、その原因である脳波の一部を取り除いたものを音と光で患者に与えると、改善が見られた。
しかしレーザーで計測される脳波はあまりにも複雑で、そこに音楽家であるジェローム・ビショップが協力することになり・・・。
あの「聖者の行進」である(笑)
前世紀の遺物
小惑星帯の中でブラックホールに遭遇してしまった宇宙炭鉱船の乗員2人は、なんとかして地球に連絡を取ろうとするが通信機も破壊されており・・・。
オチは想像つくが、本作が発表された非SF誌の読者ならどうだろう?
三百年祭事件
2076年7月4日。世界は統一された連邦制になっていたが、「地方」として元の国の文化も色濃く残っていた。
そんな世界でアメリカの建国300年祭が行われるが、大統領の姿が一瞬で消え・・・。
オチは読める・・・というかオチなのかどうか、ちょっとよわくわからなかった(汗)
発想の誕生
タイムマシンを発明した男が約50年前のアメリカに・・・。
アメージング・ストーリー誌50年記念号に掲載されたもので、ほとんど楽屋落ちみたいなもの(笑)
面白いのもそうでないのも収録されているが、やはり「バイセンテニアル・マン」が飛び抜けている。
ところで本書の中のいくつかの作品もそうだが、アシモフの作品はどうやらロボットが登場しないものでもUSロボット・アンド・機械人間社が存在する同じ世界線で展開しているものが多いようだ。
誰か調べ上げて年表とか作ってないのかしら。
20250913(mixi日記より)
20250913
アンドリューNDR114
クリス・コロンバス監督
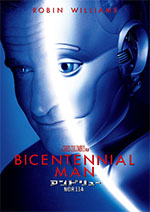 近未来、マーティン家に運ばれてきたロボットNDR114はアンドリューと名付けられた。
近未来、マーティン家に運ばれてきたロボットNDR114はアンドリューと名付けられた。
ある日アンドリューがマーティン家の次女であるアマンダの大切にしていたガラスの馬を壊してしまい、代わりにアンドリューは木彫りの馬を作る。
驚いたマーティンはアンドリューをメーカーであるロボテクス社に連れて行くが、不良品扱いされて頭にくる。
やがてアンドリューは作品の販売で収入を得・・・。
原作を読んだら映像を見るシリーズ。
おそらく15年ぶりくらいであんまり覚えていなかったのだが、なんでも批評家にはこき下ろされて興行成績も散々だったらしいが、そんなこき下ろすような悪いところは一切なく、むしろすごくいい映画だった。
原作ファンからすれば、アシモフらしい落ち着いた雰囲気はしっかり味わえるし、映画ならではのアレンジ部分も納得できるもので効果的だったと思う。
リトル・ミスが小さいのも大きいのもしっかり可愛いのもわかってる感じ(笑)
映画ならではというところでは原作には一切出てこない浜辺のシーンがやたらに多いとか、このへんは監督の好みなのだろう(笑)
ラスト近くのセックスや恋愛関連の展開も、映画としてなら悪くないアレンジだと思う。
オリジナルキャラのガラテアもいい感じ。
特筆すべきはアンドリューのロボットボディのデザインで、かっこよくはないが特別かっこ悪くもなく、いかつくもなく、ちょっとロビン・ウィリアムズにも見える上にちゃんと動けるというある意味究極のプロダクトデザインである。
それにしても似たようなテーマのスピルバーグの「AI.」がそこそこ評価され、本作がそうではないというのは納得がいかない。
「A.I.」こそ糞味噌に言うべき映画だと思う(笑)
1つ気になったのは最後にガラテアがやったことで、これは完全にロボット三原則第1原則に反している。
20250914(mixi日記より)
20250914
敵は海賊・A級の敵
神林長平著
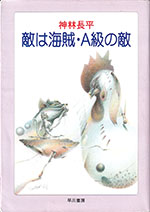 海賊課の1級刑事セレスタン・エアカーンはでかい図体で食い意地が張っており、銃の腕も一流だが繊細なところがあり、かつてはラジェンドラに乗っていたのだがラジェンドラの遠慮のない台詞に耐えられずにチームを解消し、現在は自律型装甲服エクサスを相棒に、単独で任務についていた。
海賊課の1級刑事セレスタン・エアカーンはでかい図体で食い意地が張っており、銃の腕も一流だが繊細なところがあり、かつてはラジェンドラに乗っていたのだがラジェンドラの遠慮のない台詞に耐えられずにチームを解消し、現在は自律型装甲服エクサスを相棒に、単独で任務についていた。
そのセレスタンが主に相手にしている海賊はラクエシュ・ホッチといい、詐欺が得意なケチな男だったが、ラクエシュを締め上げることで情報が得られるのだ。それと食べ物が。
ところでマグファイヤ・キャラバンがなにものかに破壊された。
実はマグファイヤは海賊であり、かつてヨウメイとも関わりがあった。
マグファイヤを破壊したものは海賊課でも海賊でもなく、正体不明だった。
セレスタンはその調査のために海賊がチャーターしたボロ船に乗り込み、ラジェンドラの一行も支援することになるが・・・。
今回はセレスタンという刑事がメインで、海賊もラクエシュの視点が多いなど、いつもと全然違う雰囲気でなかなか楽しめた。
いつもはなにしろラジェンドラのチームは滅茶苦茶すぎてストーリーが霧散しそうになるのだが、本作はそういうことがないので少し普通のSF冒険小説っぽくなったというか(笑)
まあアプロはいつもの通りなので相変わらず滅茶苦茶なところは滅茶苦茶なのだが。
問題の「A級の敵」はこれまた著者らしいやっかいなやつで、結局なんで◯◯◯◯なのかの理由もよくわからないのが面白い(笑)
ちょっと映画版スタートレックのようでもあったりする。
20250920(mixi日記より)
20250920
ゲゲゲの鬼太郎 60's 第13~14話

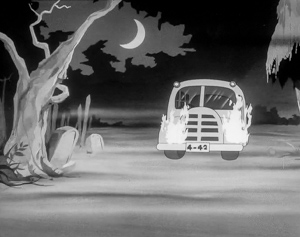
原作ではナレーションで済ませたところを映像で再現したのと、ねずみ男の件以外はおおむね原作通り。
こういう鬼太郎が謎めいた力で人間に酷い目にあわせるエピソードは、初期原作っぽくてけこう好き。
第14話 水虎


山村に住む孤児の少女百合子は、はちみつを作れるようになったのでこれからは1人でも生きていけると両親の墓に報告する。
不気味な叫び声に導かれ、近くにあった壺に封じられていた何者かを助け出してみると、それは500年前に中国からやってきた恐ろしい妖怪水虎で、あらゆるものの水分を奪って破壊しはじめ・・・。


驚いたことにストーリー、登場人物、水虎の能力や姿と、あらゆるところが原作とは異なる。
メインはとてもいい子で可愛くて色っぽい百合子ちゃんだが、もちろん原作には登場せず、原作では身体が水でできているという以外はこれといった見せ場のなかった水虎の能力が、木を舐めたら枯れ、地面を舐めたら地割れが発生というすさまじさで、世界を滅ぼしかねないスケールに(汗)
またその姿も原作ではよれっとした老人のようなものだったが、こちらではまさに虎そのもので勇ましい。
水虎の倒し方だけは原作と同じだった。
なんでこんなことになったのだろうか?
他のエピソードの原作の再現度からすると、同タイトルで全く異なる原作が存在しているのではないかと疑ってしまう。
20250921(mixi日記より)
20250922
地球からの贈り物
ラリイ・ニーヴン著/小隅黎訳
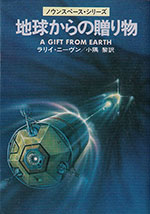 を昨日読んだ。
を昨日読んだ。
えり好みしなさすぎるラムロボットによって人類の居住に適していると判断された鯨座タウ星は超高温と有毒大気の惑星だったが、地表から40マイルも突き出しているマウント・ルッキッザットの山頂平原だけは確かに居住可能だった。
そのマウント・ルッキッザットに人類が植民をはじめてから約300年後、マシュー・ケラーは追いすがる統治警察の手を逃れ、マウント・ルッキッザットから飛び降りた。
それでもマウント・ルッキッザットはこれまで通りで変化は無かったが、新たなラムロボットが運んできた地球からの荷物は大きな変化をもたらそうとしていた。
ノウンスペース・シリーズの長編。
主にマシューの甥であるマシュー・リイ・ケラーの視点で進むが、どちらかといえばマウント・ルッキッザットの歴史の転換点全体がメインの群像劇という印象も。
ノウンスペース・シリーズは非常に長い歴史を描いていて、その中でも最も悲惨なのが臓器移植が社会の根幹を占めた時代で、交通違反でも死刑になって臓器移植用のパーツにされてしまう(汗)
本作はそんな時代のしかも超光速航法技術もない上でのコロニーが舞台であり、より悲惨なことになっている。
移民船の乗員はそのまま貴族階級となり、コールドスリープされて運ばれてきた移民たちは彼らに奉仕する立場で、もちろん反逆罪は即座に死刑で臓器パーツにされてしまうのだ。
そんな世界の変革の流れが描かれるわけだが、化夢宇留仁的には今まで読んだノウンスペース・シリーズの中ではもう一つに感じた。
何と言ってもニーヴンの魅力は面白い異星人なので、それが一切出てこない上に上記のようななかなか悲惨な状況で一気に盛り上がるという感じにならないのだ。
また主人公マシューがその能力の関係もあってヒーローっぽい要素が皆無なのも影響していそう。
その分2人のヒロイン(?)は超ヒーローっぽいが(笑)
統治警察の長官ジーザス・ピエトロや、乗員階級で「病院」の支配者のミラード・バーレットなど、じじいで魅力的なキャラクターがいるのはなかなかよかった。
20250926(mixi日記より)
20250926
地底世界シリーズ6
恐怖のペルシダー
エドガー・ライス・バロウズ著/関口幸男訳
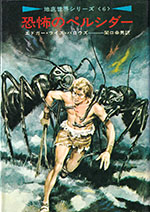 ローハールでフォン・ホルストを発見し、サリへの帰途についたデヴィッドたちだったが、途中広い川を筏で渡っているときに女ばかりの凶暴な部族に襲撃され、デヴィッドが拉致されてしまう。
ローハールでフォン・ホルストを発見し、サリへの帰途についたデヴィッドたちだったが、途中広い川を筏で渡っているときに女ばかりの凶暴な部族に襲撃され、デヴィッドが拉致されてしまう。
デヴィッドが愛するダイアンの待つサリへ帰るための道筋には、例によって想像を絶するほどの大冒険が立ちはだかっているのだった・・・。
まず初っ端からびっくりさせられたのがペルシダー第1巻当初のデヴィッドの年齢。
20歳だそうな。アブナー・ペリーに地下試掘機を開発する資金を提供していた鉱山主が20歳(汗)
ほんとに最初からそんな年齢設定だったか?
化夢宇留仁は少なくとも30代から40代だと思って読んでいたぞ(汗)
そのデヴィッドが主役の物語は2巻から3冊はさんで超久しぶりで、しかも2巻では皇帝におさまっていたのが本作ではいつものバロウズ節に放り込まれるのでなかなか大変そうである(笑)
そして相変わらず繰り返されるあまりにも絶望的な様々な状況。
今回は途中でとんでもない偶然による驚きの出会いが用意されているが、その後はやっぱり別れ別れになっていつもの苦難になだれ込んでいく(笑)
バロウズの特徴だが、1冊の物語に通常の4冊分くらいのアイデアをぶち込んでくるので、毎度目まぐるしいことおびただしい(笑)
例えば表紙(それに口絵までも)で目立っている巨大蟻だが、こんなの物語の通過点のほんの一部にすぎないのだ(笑)
それにしても今回はいつもに増してすれ違いシチュエーションが繰り返されてすごかった(汗)
また本作ではもはやほとんどノリで書いていたのか、伏線の回収で納得のいかないところが散見された。
その中でも気になったのが彼女が1人でサリに向かった理由だが・・・まあとにかく面白いので細かいことはいいか(笑)
20251003(mixi日記より)
20251003
ゲーム・オブ・デス
セバスチャン・ランドリー監督
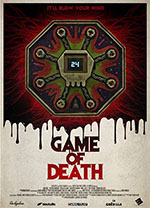 郊外の別荘のような建物でドラッグとセックスにまみれたパーティーを楽しむ若者たち。部屋の片隅でニンテンドー64の隣りにあったレトロな電源式ゲーム「死のゲーム」をやってみる。
郊外の別荘のような建物でドラッグとセックスにまみれたパーティーを楽しむ若者たち。部屋の片隅でニンテンドー64の隣りにあったレトロな電源式ゲーム「死のゲーム」をやってみる。
ゲームは24という数字を表示した。
制限時間内に表示された数だけの人を殺せばクリア、殺せなければ死ぬのはプレイヤーで、カウンターが0になるか、プレイヤーが全員死ねばゲーム終了である。
そんなことを信じるわけもなくビール一気飲み大会をしていたが、突然1人の頭が爆発し・・・。
要するにジュマンジのスラッシャー版である(笑)
面白くなりそうなアイデアだが、化夢宇留仁的には残念な結果になった。
とりあえずこんなバカバカしいテーマの場合、とことん狂うかとことん理詰めのどちらかであれば面白くなると思うのだが、そのどちらにも行けずに中途半端なところに着地してしまっている。
化夢宇留仁が期待していたのはルールはルールとして割り切ったやつが殺しを楽しみだす展開だったのだが。
この手の1アイデア作品は落ち次第でど~~ん!と評価が上がる場合もあるのだが、それも全然驚きのない展開でションボリ(汗)
また劇中の音楽がどれも素人臭い学生作品みたいで酷かったのも大きなマイナスポイント。
これはほんとに酷い。
唯一よかったのはサイコパスの彼女役のビクトリア・ダイアモンドが非常に可愛かったことで、これだけで★+1点(笑)
BHE(最高点5)(面白い殺し方/3)(可愛い女優&裸/3)(面白いキャラクター/1)
20251004(mixi日記より)
20251004
坊っちゃん
夏目漱石著
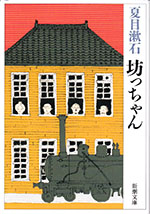 子供の頃から無鉄砲でバカ正直な江戸っ子である「坊っちゃん」は、兄の残してくれた600円で物理学校に通い、卒業後四国松山の中学校に数学教師として務めることに。
子供の頃から無鉄砲でバカ正直な江戸っ子である「坊っちゃん」は、兄の残してくれた600円で物理学校に通い、卒業後四国松山の中学校に数学教師として務めることに。
ところがそこにはたちの悪い生徒たちと面の皮の厚い教師たちが・・・。
冒頭坊っちゃんの小さい頃のエピソードとして、西洋製のナイフを見せびらかしていたら光るだけで切れそうもないと言われ、なんでも切れると答えたところ、そんなら君の指を切ってみろと言われたので、「できら~」とばかりに親指の骨に達するまで切ってしまったというのがあっていきなりドン引き(笑)
キチガイやん(笑)
しかしその後は大人になったこともあってそこまでキチガイじゃなくなって一安心(笑)
結果的には非常に面白く読めた。
まずテンポが非常にいい。
江戸っ子の坊っちゃんの一人称なのと、各シーンが少しでも助長になりそうになると即座に切り替わるせいだと思う。
正義の人であると同時にやはりちょっとキチガイなので(笑)、とにかくやること思うことが極端なのもテンポを産んでいる要因の1つだろう。
物語としては想像していたのと違い、これまたなかなか極端で、最後は剣客商売で見たような展開になったのには驚いた。
その結果は江戸時代と明治時代ならではの違いがあり、理不尽は理不尽なままだが、ある意味坊っちゃんは江戸時代の生き残りのようなところもあるのかもしれない。
またここでは書かなかったが坊っちゃんを育ててくれた清さんの存在も、過去への憧憬の象徴のようでもある。
化夢宇留仁が全編通して最も面白いと思ったのは明治当時の文化そのもので、お金の価値では月9円50銭でなかなかの邸宅が借りられるとか、まだ氷が手に入りにくいので氷水が1銭5厘するとか、じゃあマグロの刺身が普通に出てくるがどうやって運んでいたのだろうとか、引き出しから生卵が出てくるとか(笑)
他にも町や建物の描写など、どれも非常に興味深くて面白かった。
一番驚いたのはマドンナの顛末で、まさかその後◯く◯◯◯◯いとは予想外だった(笑)
20251009(mixi日記より)
20251009
ローダンシリーズ40
核地獄グレイ・ビースト
クルト・マール著/松谷健二訳
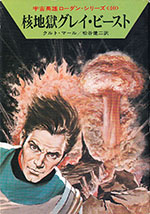 核地獄グレイ・ビースト
核地獄グレイ・ビースト
ローダンがとうとうアルコンへの総攻撃を決断した。
しかし艦隊集結中にグレイ・ビーストに帰還した巡洋艦リゲルの固有振動ダンパーに故障が生じ、グレイ・ビーストがアルコンに見つかってしまい・・・。
危機から危機への息をもつかせぬバロウズばりの展開でなかなか面白い。
しかし前にトーラが脱走したときと同じく脇道なのも間違いないので少々微妙なのと、いくつか納得のいかない点が。
まず摂政の判断だが、血眼になって探している地球の手がかりになるかもしれない惑星をいきなり攻撃し、あまつさえ調査もせずに惑星ごと焼き尽くしてしまうなど、超高度な判断力を備えたコンピュータではあり得ないと思う。
対するローダンの対応も、戦力的に話にならないのはわかっているのに防戦した上に、相手は惑星ごと破壊できるとわかっているのに一部メンバーは地下にこもるというのも全く納得がいかない。あそこはいかに犠牲者を少なくして迅速に脱出するかしか考えることは無かったはず。
また暗号をあいつらが気づいて回収に来るというのもありえないと思った。
ドルーフの本拠にて
ドルーフに囚われた4人はなんとか脱走しようあの手この手でがんばるが・・・。
危機的状況が続くので退屈はしないが、相変わらず脇道なので微妙。
こういうときこそブリーの見せ場がほしいのだが・・・(汗)
ちうわけで急展開で本筋で大規模なイベントが発生するかと思いきや、脇道の大冒険前後編なのだった(汗)
次巻に期待・・・(汗)???
20251017(mixi日記より)
20251017
サンゴ海の戦い 史上最初の空母戦
エドウィン・ホイト著/志摩隆訳
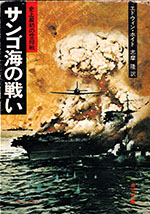 1942年。連戦連勝を続ける大日本帝國軍は、ポートモレスビー攻略作戦の準備を進めており、サンゴ海には空母「翔鶴」「瑞鶴」をはじめとした機動部隊が集結しつつあった。
1942年。連戦連勝を続ける大日本帝國軍は、ポートモレスビー攻略作戦の準備を進めており、サンゴ海には空母「翔鶴」「瑞鶴」をはじめとした機動部隊が集結しつつあった。
もちろんそれを連合軍が放おっておくわけもなく、同じく空母「ヨークタウン」「レキシントン」を主体とした部隊が日本軍の動きを警戒しており、ここに史上初の空母対空母の対決が始まろうとしていた・・・。
史料を調べ上げた上で構築されたいわゆる戦記物で、一般的な小説とは一線を画す内容。
とてもよかったのは著者がクレバーな視点に努めているところで、日米どちらも正義とか悪とかいう感じは一切無く、それぞれが与えられたものを活かして全力を尽くしているのが伝わってくる。
ただしそのせいもあって壮絶に読みにくい(汗)
なにしろ空母戦というのは空母、艦載機という最小単位に絞ってもそれぞれの視点は幅広く、更に1隻の空母の中でも提督、館長、士官、下士官と、それぞれの限られた視点から見る風景は全く異なる。
そもそも空母戦というのは敵の姿を見ないままで戦う言い換えれば史上初の無視界戦闘ということでもあり、当時の限られた情報収集能力のせいもあってまさに霧の中でもがいているような特殊な戦場なのだ。
というわけで当時の記録にあった様々な視点による状況や無線でのやり取りなどが入り混じり、同じ戦闘でも日米はもちろん船長から見た状況、水兵から見た状況、パイロットから見た状況など、全く異なるものが時には時間を遡って書かれたりする上、クレバーに努めたせいか「しかし」のあとの文章がその前の文章を否定していないように思えたりと、なかなかの混乱ぶり。しかしそこがまた当時の戦場の雰囲気を伝えているようでもある。
サンゴ海の戦いは史上初の空母戦というだけではなく、歴史的にも非常に重要な戦いで、米軍が連戦連勝の日本軍と戦って初めて痛み分けまで持ち込んだ戦いでもあり、その後のミッドウェー海戦での決定的な勝敗はこの戦いがあったからこそ実現したものとも考えられるのだ。
細かい描写という点でも流石に大量の史料を調べた上で書いているだけあって、急降下爆撃の命中率の高さや、米空母の頑丈さ、米軍の魚雷の不良率の高さ(笑)など、非常に見どころが多い。
また本作では空母と艦載機以外の機動部隊の様々な要素もしっかりと取り上げており、特に米軍の給油艦ネオショーの顛末などはそれだけで1本の小説が書けそうである。
そして空母レキシントンの不幸な(日本軍からしたら大ラッキーな)結末は、まるで前に読んだ「十四分の海難」のようでもあり、非常に興味深かった。
というわけで非常に読みにくいが内容があまりにも興味深く、またイケイケだった頃の日本の凄さも垣間見えたりして、面白い本だった。
ちなみにまあまあ渋い戦記物の表紙としてはあまりにもかっこよすぎるので確認してみたところ、案の定生賴大先生の筆だった(笑)
20251023(mixi日記より)
20251023
坊っちゃん
前田陽一監督
 を昨日観た。
を昨日観た。
1977年の映画版。
子供の頃から無鉄砲でバカ正直な江戸っ子である「坊っちゃん」は、学校卒業後四国松山の中学校に数学教師として務めることに。
ところがそこにはたちの悪い生徒たちと面の皮の厚い教師たちが・・・。
原作を読んだら映像を観るシリーズ。
と言っても坊っちゃんは何度も映画化されているのだが、古い映画はほとんど見る手段が無く、一番手軽に見られるのが本作だった。
主演は中村雅俊で、化夢宇留仁の幼少時にドラマなどで大活躍していたのが懐かしい。
ところで映画ともなると、原作が書かれた時代に加え、映画が制作された時代の味も加味されるわけだが、当時からしたら過去の時代を扱った映画の画面が非常に豪華感があるのはなぜだろう?
主役はドラマで見慣れた顔だけあってそうでもないが、それ以外はキャストもセットも映像自体も、化夢宇留仁からすれば100億円以上かけて作られているハリウッド映画と並ぶくらい豪華に見えるのが不思議。
で、内容だが、原作を咀嚼しまくって再構築されている感じで、あらゆるところが異なるのに、あらゆるところが原作と同じに見えるというある意味では映画化の見本と言えるようなアレンジがされていた。
例えば山嵐とは四国に向かう船上で出会い、上陸後は人力車のレースになったり、バッタ事件直後に夜中のドンドン事件はカットされて職員会議のシーンになったり、原作では出てきただけだったマドンナが、こちら(松坂慶子。とても美しい)では大活躍するか・・・と思わせてやっぱり全然だったり(笑)
原作と違うのは生徒たちの扱いくらいで、こちらはもう少しマシな人間に描かれている(笑)
ちうわけでテンポがよくてなかなか面白かった。
しかし原作からしてテンポがいいのが取り柄みたいな物語だと思うし、坊っちゃんという作品自体がここまで大きく何度も取り上げられる理由は化夢宇留仁にはよくわからない(汗)
20251024(mixi日記より)
20251024
BACK 記録&感想トップ NEXT
HOME
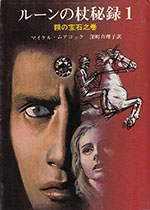 文明が崩壊し、剣と魔法が支配するようになった今から1000年ほど未来の地球。
文明が崩壊し、剣と魔法が支配するようになった今から1000年ほど未来の地球。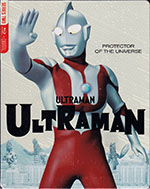














 男盛り
男盛り 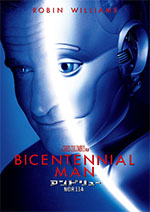 近未来、マーティン家に運ばれてきたロボットNDR114はアンドリューと名付けられた。
近未来、マーティン家に運ばれてきたロボットNDR114はアンドリューと名付けられた。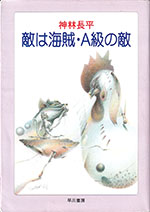 海賊課の1級刑事セレスタン・エアカーンはでかい図体で食い意地が張っており、銃の腕も一流だが繊細なところがあり、かつてはラジェンドラに乗っていたのだがラジェンドラの遠慮のない台詞に耐えられずにチームを解消し、現在は自律型装甲服エクサスを相棒に、単独で任務についていた。
海賊課の1級刑事セレスタン・エアカーンはでかい図体で食い意地が張っており、銃の腕も一流だが繊細なところがあり、かつてはラジェンドラに乗っていたのだがラジェンドラの遠慮のない台詞に耐えられずにチームを解消し、現在は自律型装甲服エクサスを相棒に、単独で任務についていた。



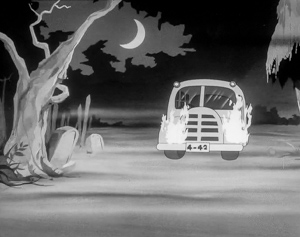




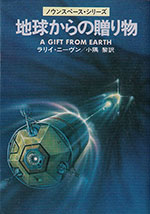 を昨日読んだ。
を昨日読んだ。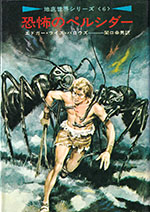 ローハールでフォン・ホルストを発見し、サリへの帰途についたデヴィッドたちだったが、途中広い川を筏で渡っているときに女ばかりの凶暴な部族に襲撃され、デヴィッドが拉致されてしまう。
ローハールでフォン・ホルストを発見し、サリへの帰途についたデヴィッドたちだったが、途中広い川を筏で渡っているときに女ばかりの凶暴な部族に襲撃され、デヴィッドが拉致されてしまう。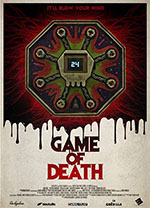 郊外の別荘のような建物でドラッグとセックスにまみれたパーティーを楽しむ若者たち。部屋の片隅でニンテンドー64の隣りにあったレトロな電源式ゲーム「死のゲーム」をやってみる。
郊外の別荘のような建物でドラッグとセックスにまみれたパーティーを楽しむ若者たち。部屋の片隅でニンテンドー64の隣りにあったレトロな電源式ゲーム「死のゲーム」をやってみる。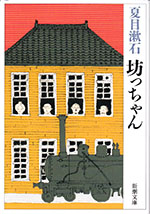 子供の頃から無鉄砲でバカ正直な江戸っ子である「坊っちゃん」は、兄の残してくれた600円で物理学校に通い、卒業後四国松山の中学校に数学教師として務めることに。
子供の頃から無鉄砲でバカ正直な江戸っ子である「坊っちゃん」は、兄の残してくれた600円で物理学校に通い、卒業後四国松山の中学校に数学教師として務めることに。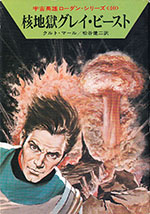 核地獄グレイ・ビースト
核地獄グレイ・ビースト 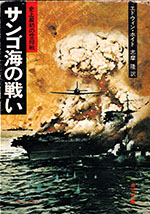 1942年。連戦連勝を続ける大日本帝國軍は、ポートモレスビー攻略作戦の準備を進めており、サンゴ海には空母「翔鶴」「瑞鶴」をはじめとした機動部隊が集結しつつあった。
1942年。連戦連勝を続ける大日本帝國軍は、ポートモレスビー攻略作戦の準備を進めており、サンゴ海には空母「翔鶴」「瑞鶴」をはじめとした機動部隊が集結しつつあった。 を昨日観た。
を昨日観た。